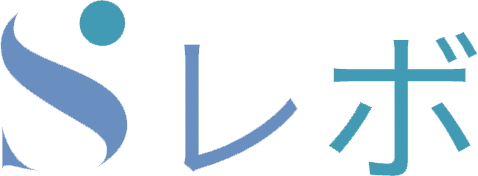ペットショップの鳥類コーナーで一際愛くるしさが目立つ「文鳥」。
つぶらな瞳やおもちみたいなフォルムで人気の鳥類ですが、初めて飼う時に何が必要か知っている人は少ないんじゃないでしょうか?
エサやケージはもちろん、その他にどういった物がいるのか?…ペットショップにいきなり行っても困惑すると思います。
そこで、この記事では初めて文鳥を飼おうと思っている人が知りたい情報をについて徹底解説しました!是非参考にしてみて下さい。
文鳥の特徴は?

文鳥は「スキンシップがとりやすい、手乗りもすぐにできる、マンションやアパートでも飼育しやすい」ことで人気のペットです。
また自分の名前もよく理解できるため、こちらの声がけにもすぐに反応してくれるとても賢い鳥です。なのでとても愛着が沸きます。
その反面、かなり繊細な性格でもあるので、環境の変化や大きな音、見慣れない大きな物、棒状の物、色の濃い物などにも反応してしまいます。
文鳥の寿命は?

| 平均寿命 | 8年~10年 |
|---|
文鳥はどのくらい生きているのでしょうか。結論から申しますと、文鳥の平均寿命は「8年~10年」と言われています。
ただ、オスとメス、文鳥の種類によっても異なってきます。8年から10年の文鳥もいれば、7年前後などの文鳥もいますし、飼育環境によってもかなりの差が出てしまいますので、一概に言うことはできません。
しかし、適切な環境を整えることで、寿命が延びることがあります。そのため、8年〜10年と大きく幅が開いていますね。
文鳥の年齢と人間の年齢の比較
文鳥はおよそ1年で人間の20歳前後と言われます。つまり大人になります。産まれてわずか1年間の成長がとても著しく、この間にどのような生活環境で育ったかにより大きく左右されてきます。ちなみに、比喩的でありますが、8年で人間の80歳と考えられています。
オスとメスの寿命の違い
文鳥はオスの方が長生きする傾向があります。それは、メスは出産の影響により体力を著しく消耗することで、寿命を縮めてしまうことが多いからです。
種類による寿命の違い
文鳥の種類には、自然にいるノーマル文鳥を始め、まだら模様の桜文鳥、色素が抑えられた白文鳥、比較的新しい品種のシナモン文鳥やシルバー文鳥と代表的な種類で5種類あります。
この中ではノーマル文鳥と桜文鳥が長生きしやすいです。それは、色素の問題があり、白文鳥シナモン文鳥、シルバー文鳥は色素が薄く日光に弱いためです。
そのため、適切な環境を構築するのに難しいと言えます。ただ、適切な管理を行った結果、白文鳥が18年生存したという報道や記録もあるため、飼育環境によっては白文鳥などの色素が薄い文鳥でも長生きできる可能性はあります。
文鳥はとてもデリケートな鳥
先ほども述べましたが、文鳥はとてもデリケートであります。また体温が42度と高いため、これを維持しなければなりません。しかし、維持するために室温をあげると、年に2度しかない発情期が常時発生してしまうなど、リスクが発生してしまいます。
日光浴についても先述のとおり品種により大きく変わってきます。それぞれの品種に合わせて日光浴をさせるようにしましょう。
次に、タバコの煙などによる気道炎をおこしやすいですので、空気環境の整備も必須です。
またケージの中を清潔に保つことと、水浴びが好きなので、水浴びをすることで清潔を保つことができます。
なので、そのような環境づくりも大切ですし、エサは専用の餌以外を与えないなど管理が必要です。
文鳥は環境により平均寿命である8年から10年をかなり延ばすことが出来ます。これは種類に関係なく、当てはまります。
上記のとおり環境を整備し、爪切りなどもちゃんと実施することで寿命を延ばすことができます。
寿命を延ばすだけでなく、しっかりお世話をすることで、文鳥も懐いてくれるのでより愛着が湧くようになります。
種類によっても色鮮やかで小さくて色彩も可愛いです。自然の文鳥は自然での生活を、ペットとして飼うならばしっかりとした知識を持ち、ちょっとした変化を見逃さず、管理行動を心がけることが大切です。
文鳥の種類について

文鳥には色々な種類がいます。今回はその中でも代表的な5種類の文鳥について解説していきます。
解説する5種類がこちらになります↓
- ノーマル文鳥
- 白文鳥
- 桜文鳥
- シナモン文鳥
- シルバー文鳥
それではそれぞれの種類について見ていきましょう。
ノーマル文鳥

ノーマル文鳥はその名の通り、一番オーソドックスな種類です。野生に最も近いと言われていおり、黒・グレーがメインの色です。ただし、お腹の部分にはベージュが入っています。
文鳥の中でも一番体が丈夫で初心者でも育てやすい種類です。
白文鳥

白文鳥は愛知県弥富市が発祥と言われる種類です。
全身は美しい純白の色をしていて、色素を抑える遺伝子が発現するという突然変異によって真っ白になっています。
その色の白さとふんわりした感じからよく「おもち」や「大福」のようだと言われる可愛いフォルムも人気です。
真っ白なので体が弱いと思われがちですが、体は丈夫です。また、眼がぶどう色をしているところも特徴の1つです。
桜文鳥

桜文鳥は一番広く世に出回っている文鳥の種類で、白文鳥と野生のノーマル文鳥を掛け合わせることで生まれました種類です。
胸の部分の白い模様が桜のように美しいという理由が名付けの由来になっています。
桜文鳥の特徴は白い頬、真っ黒な頭部や尻尾、真っ赤なくちばしです。とてもはっきりとした色をしています。
また模様の出方には個体差があるので、白色の入り方が個体によって違います。
体格が良く、しっかりしている子が多く、活発で負けず嫌いな性格の子が多いと言われます。
シナモン文鳥

シナモン文鳥はセピア色や茶色っぽいカラーが特徴の文鳥で、とても優しい色をしています。
黒色を出すメラニン色素が不足しているため、このような色になっています。ただし、中には色合いが濃い文鳥もいて、そうした文鳥はモカブラウン文鳥と言われています。
体は少し弱めですが、ペットとして飼うことは可能です。飼育するときはメラニン色素がないので、長時間日光を浴びさせることは危険です。
シルバー文鳥

全体的にグレー色をしている文鳥です。ただ色の出方には個体差があり、濃いグレーの文鳥や薄いグレーの文鳥がいます。
シルバー文鳥も色素の一部が不足しているため、直射日光に弱いという性質があります。
性格はしっかりしていて、落ち着いた性格の子が多いと言われます。
また文鳥は種類によって性格が違うというよりは、個体差による性格の違いが大きいです。
同じ桜文鳥でも性格は全然違うこともよくあります。全体的に多い性格としては、気が強い、好奇心が強い、嫉妬心が強い、短気、愛情が強い、人懐っこいという性格です。
特にさし餌を卒業した後に優しく接すると懐きやすいと言われます。懐くと飼い主のあとを一生懸命ついてきたり、手の上や足の上に乗ってきたりもします。
また、手の中や肩の上でリラックスして眠ることも多いです。愛情を持って接するとその分愛情をしっかり返してくれるのところは文鳥の可愛い魅力です。
文鳥の値段について

人懐っこく丈夫で飼いやす文鳥を飼いたいと思った時に気なるのが値段。どれくらいの値段で販売されているのか気になりますよね?
文鳥は主な種類で5種類ほどいますが、どの種類も10,000円を超ることはありません。高価な動物ではないので、より飼いやすいペットですね。
ここでは5種類の文鳥の値段について解説していきます。
値段相場表
文鳥の相場がこちらです。
| ノーマル文鳥 | 2,000円ぐらい |
|---|---|
| 桜文鳥 | 2,000〜3,500円 |
| 白文鳥 | 2,500〜4,000円 |
| シナモン文鳥 | 5,000〜7,000円 |
| シルバー文鳥 | 5,000〜10,000円 |
「ノーマル文鳥」が最も安く、2,000円程度。「桜文鳥」は2,000円から3,500円前後。高騰した時期でも5,000円ほどでした。「白文鳥」は2,500円から4,000円前後。「シナモン文鳥」は5,000円から7,000円前後。「シルバー文鳥」は少し高めで5,000円から10,000円前後。
こうしてみると、それぞれの種類で値段の差がありますね。
この値段の基準はどのように決まっているのか気になりませんか?…気になる人のためにちょっとだけ説明していきます。
まず最初にペットショップが文鳥を育てている会社から仕入れてくる仕入れ値で決まります。仕入れ時の値段としても上記の順に高くなります。そこからペットショップは育成の手間等があったり、だいたい仕入れ値の倍ほどで販売していることが多いです。
実は文鳥は一般的に、生育の手間や餌代の関係で雛に近いほど値段が安くなる傾向があります。
雛がたくさん入荷されるのは繁殖時期です。文鳥は昼の長さが短くなる時期に繁殖期に入ります。このことから文鳥の繁殖時期は秋から春頃です。
その時期にペットショップを覗いてみると、雛が多く入荷されているはずです。そのためお安く文鳥を手に入れたいなら、繁殖時期の秋〜春にペットショップに行ってみると安く買える可能性があります。
次に希少性があります。シナモン文鳥はメラニン色素が無く、目が赤いため希少種となります。シルバー文鳥は桜文鳥に似ていますが、全体的に体毛の色が銀色がかっています。その銀色が薄いか濃いかによっても大きく値段が変わってきます。そのため希少性が高くなります。
また、最も人気な種類が桜文鳥と白文鳥です。そのため桜文鳥と白文鳥は圧倒的に流通量が少ないため、価格が高くなりがちです。
ご注意いただきたい点としまして、値段が高いから寿命が長く丈夫と言う訳ではないということです。
例えば、丈夫さには関係ありませんが、シナモン文鳥とシルバー文鳥は他の文鳥より太陽の直射日光に弱いです。
丈夫さに関しては、種類や繁殖時期、育て方等様々な理由で変わってきます。文鳥愛好家のわたしの意見ですが、価格だけで判断せずに繁殖時期を気にしつつ、可愛い子と出会ってくれるのが一番です。
文鳥のエサについて

文鳥のエサは何を与えたらいいの?と思う方がいるかもしれません。市販で販売されている鳥用のエサをあげておけば問題ないとは思うけど、他にどういった物を食べるのか気になりますよね。
そこでここでは文鳥にお勧めなエサを「主食」と「副食」に分けて解説していきます。
主食
文鳥の主食となるエサは「シード」と「ペレット」の2種類です。それぞれどいった物なのか解説していきますね。
シード
シードは最もポピュラーなエサです。文鳥は穀物の種を主食としているため、アワやキビなどの穀物類が入ったエサを与えます。(これがシードですね)
シードは野生の文鳥が食べるエサにとても近いため、ほとんどの文鳥が好んで食べてくれます。しかし、炭水化物が多いなど、カロリーの過剰摂取には注意が必要です。
ペレット
獣医もお勧めするエサがペレットです。
ペレットは人工的に作られたエサで、文鳥に必要な栄養素がペレットだけで摂取することができます。
そのため、副菜を与えなくていいので管理が楽です。しかし、ペレットを好んで食べてくれない文鳥もいるので、その時は慣らしていく必要があります。
副食
副食は主食だけでは足りない栄養素を補うためのエサです。主にビタミンやミネラルの補給のために食べさせることがほとんどです。副食には野菜や果物、ボレー粉などがあります。
野菜
野菜は文鳥にとって必要なビタミン源です。また、穴をあけたり、文鳥にとってのおもちゃの役割も持っています。
文鳥に与える野菜としておすすめなのが、「小松菜、青梗菜、ニンジン、アスパラ、パセリ」などがあります。反対に与えてはいけない野菜もあるので、与えるときは注意しましょう。
果物
果物が好きな文鳥は多いです。ただし果物の種は中毒を起こす可能性もあるので、食べさせるのは果肉だけにしましょう。
みかん、バナナ、リンゴ、イチゴなどがよく与えられています。中にはスイカを好む文鳥もいますが、水分が多く、身体を冷やして下痢になる可能性もあるので、与えるときの量は調整しましょう。
反対に与えていけない果物は「アボカド、モモ、アンズ」です。これらは中毒を起こす代表的な果物で、特にアボカドは致命的にもなりますので、絶対に与えてはいけません。
ボレー粉
ボレー粉?何それ?という人もいると思います。ボレー粉とは、2枚貝のカキの殻を砕いて粉にしたものです。
鳥の主要なミネラル源として市販されています。主にカルシウムを補給するために必要とされています。
ボレー粉はミネラルやカリウムなども含まれているため、健康維持のために重要な役割をしてくれます。また、地着色や添加のない、自然のままのものを白ボレー粉といいます。
その他
この他にも動物性たんぱく質やサプリメントもあります。おやつとして与えたり、薬として与えたりと使い方は様々です。
文鳥を飼育するのに必要なモノは?

いざ文鳥を飼おうと思っても、何を買えばいいかわからないって思うことありませんか?
そこで文鳥を飼おうと思ったら予め以下のモノは揃えておきたいので、文鳥を買う前に参考にされて下さい。
ケージ
ケージは文鳥のお家となりますので、必ず必要です。
大きさの目安は、幅35cm✖️奥行き40cm✖️高さ40cmぐらいがおすすめ。その理由はケージの中に止まり木や餌入れ、水浴び器など、入れなければいけないものが多いからです。
特に止まり木と止まり木の間隔や、止まり木と壁の間隔が狭くなると、羽繕いもやりづらくなりますので、目安は守るようにして文鳥が過ごしやすい空間を作ってあげましょう。
ブランコ
文鳥はブランコを止まり木として認識していて、よくブランコに乗ります。乗り降りを繰り返して、結構長い時間を過ごすこともあります。また、ブランコには鈴がついているものもあるので、ブランコを揺らして鈴を鳴らして遊ぶこともあります。ブランコは文鳥の止まり木でもあり、おもちゃにもなるので便利な遊び道具です。
水浴び器
文鳥は水浴びが大好き動物です。綺麗好きな子が多いので、羽毛についた汚れなどを落とすために水浴びをします。水遊びは文鳥のストレス解消にもなりますので、文鳥の体がすっぽり入れるぐらいの大きさの水浴び器を用意しましょう。
体重計
体重計は0.1グラム単位で量れるものが便利です。文鳥が痩せすぎたり太りすぎたりしないように、日々の体調管理は不可欠です。毎日量って文鳥の変化に気づけるようにしましょう。
ヒーター
ヒーターは必須道具です。特に冬は空気も乾燥しがちですし、気温も下がります。明け方の寒さなどは文鳥にとってとても危険で、死に至る可能性もあります。20度は下回らないようにヒーターをつけて温度管理する必要があります。
餌入れ、水入れ
餌入れや水入れは文鳥が自分でひっくり返したりしないように、固定できるものが良いです。特にケージの隙間にはめ込むことができるタイプのものなら、色々な場所に配置することができるので便利です。
菜差し
青菜や野菜を差し込むためのものです。文鳥の副食になります。少ない量でも倒れたりしないよう、安定させられるものが良いです。
温湿度計
文鳥の体調管理のために必要です。気温が低すぎたり高すぎたりすると病気になってしまいますので、温湿度計を設置して気温を管理する必要があります。
特にヒナの場合は、湿度が低いと体から水分が蒸発してしまい、脱水症状を起こすこともあります。
暗幕
暗幕はケージにかけるために必要です。文鳥はどんなに遅くても午後9時には眠らせてあげる必要があります。室内に光があると眠れず、ひどい場合には肝臓肥大や脂肪肝になってしまうこともあります。光が差し込まないように暗幕はしっかりした素材のものを準備しましょう。
文鳥のひなの飼育について

文鳥はひなの頃に人間が手をかけて育てると、とても懐きます。懐いた文鳥はどこにいても飼い主のところに飛んできて、肩に止まって毛づくろいしたり。出して出してと、かごにへばりついて自己アピールしたりと、愛らしい姿に心癒されます。
そのため、ひなから文鳥を育てたいという人も多いと思いますが、文鳥のひなを飼育するには注意が必要です。
ここでは実際に文鳥のひなを育てた経験から語る注意点を含めてひなの育て方について解説していきます。
ひなを育てるのに必要な道具
まずは、文鳥のひなを育てるときに必要なもの(環境を整える)を見ていきましょう。
【巣箱】
巣箱は木でも紙でも可能です。大切なのは薄暗い空間を作ってあげることです。フタがあるものが理想です。
【巣材】
新聞紙を切り裂いたものを用意しましょう。ふん尿で汚れるので、2〜3日で交換してください。
【鳥用スポイト】
餌を与えるときに必要です。ストローで代用を考える人もいますが、専用のものでないと、与えにくいです。餌を与える期間もそこそこ長いので、鳥用スポイトはおすすめです。
【スポイト専用カップ】
粟玉などをスポイトで取り入れやすい形状になっているカップです。初心者は必ず用意した方が良いです。
【ヒーター(寒い場合は)】
電気をあててあげるだけでも良いです。冬など冷える場合は、羽が生えそろっていないひなにとっては、死を意味します。ヒーターで外側から温めたり、ペットボトルをタオルに包んでおいてあげたり、暖を取れる環境を整えてください。
【ひなにエサを与える(さし餌)】
ペットショップで販売されている文鳥のひなは、卵から孵化して約二週間の状態でおかれているものがほとんどです。自分でえさを食べられるようになるには、まだ一か月ほどかかります。
その間にエサを与えることで、ひなが人間を親として認識していくので、手乗りにしたいと思う人はこの間にしっかり世話をしてください。時々手に乗せて、羽をなでたり、背中をなでると、人間とのスキンシップを好む甘えん坊が育ちます。
エサは、粟玉に栄養剤(パウダー)を混ぜたものを加えて、38度~40度のお湯でふやかします。親鳥が与えるエサと同じように暖かくなければ、ひなはエサを食べませんので、ふやかすときのお湯の温度に気を付けてください。
また、小松菜などの青菜もすりつぶして混ぜ合わせると、毛のつやが良くなります。
エサをあげる時間は、3時間~4時間に一度。体が小さいので、一度に多くは食べられないのでこまめなエサやりが必要となります。ある程度の大きさに成長してくると、自然に食べない時間が出てくるのでその時は、エサやりの回数を見直してください。
昼間仕事で家を留守にしがちな人は、ひなから育てるのは命にかかわることなのでおすすめしません。文鳥のひなを飼うときには、多くの人の手を必要としますので、自分の生活スケジュールとあわせて、自宅にお迎えを考えてください。
さし餌は突然終わりが来ます。それまで手間だなと感じていても、ひなが家に来て一か月もすると自分から食べなくなります。自宅で生まれたひなの場合は、もう少しさし餌が必要です。
文鳥は自分でえさを食べられるようになるのは、卵から出てきて約一か月半から二か月です。そのあとは、自分でえさを上手に食べるようになってきます
もしなかなか、餌をうまく食べられない子がいる場合には、少しトレーニングをしてあげましょう。止まり木や指に止まらせて、少量の乾燥した粟玉を口に入れるところからスタートします。
さし餌のように水分が含まれていないので、水は別に用意しましょう。粟玉をくちばしでわって、中身をうまく食べられるようになると、ひな自身が餌の食べ方を覚えていきます。スポイトを見せて、口を開けるようならまだまださし餌が必要です。そのうちスポイトには見向きもしなくなります。
餌を与えられる期間は短いです。貴重な時間を楽しみましょう。
ひなが自力で飛べるようになったら
ひなは、本能で羽を動かし始めます。その時にいつまでも巣箱で過ごしていると、腕が曲がってしまったりするので、ゆったりめの広さのカゴに移しましょう。
また寝床は、ツボ巣を入れてあげるとうまく中に入って休むことを覚えます。エサと水も一緒に入れておくと、自分のタイミングで食べるようになります。
飛ぶ動作を始めたら、一日の間に時間を見つけて外に出して運動させましょう。この時、必ず部屋の窓やドアはしめておいてください。高い位置にある家具のすきまなどに、入り込む危険もありますので、危なくないように見守ってあげましょう。
高い位置まで飛べるようになってきたら、万が一に備えて風切り羽を切っておきましょう。風切り羽とは、左右の羽の長い部分です。切る長さによって、飛ぶ高さが変わります。自分で切る自信のない人は、一度獣医に相談すると良いでしょう。
なぜ飛ぶための羽を切るのかというと、文鳥を外に出して遊ばせていると予想外のことが起きて外に逃げてしまうことがあるからです。多くの文鳥を飼育したことがある人は、経験していることがほとんどです。
一度外に出てしまうと、ほとんどが帰ってきません。そうした危険を避けるためにも、予め予防的処置を施しましょう。うちは絶対大丈夫という保証は、どこにもありませんので、大切な家族を守るために必要な措置です。
文鳥を飼育する時の注意点について

文鳥を飼っていると色んな問題に対峙することがあります。それらに対策するためにも気をつけるポイントを知っておくことで予防することができます。
ここでは文鳥を飼育する時に気をつけておきたいポイントについて紹介していきます。
室温の調整
熱帯地方原産の文鳥は比較的暑さに強い鳥ですが、暑すぎると衰弱してしまいます。反対に寒さには弱いので、室温は一定になるように保ちます。夏はケージを風通しの良い場所に置き、冬はペット用ヒーターなどで室温を調整しましょう。
忘れがちですが、湿度も非常に重要です。ヒーターなどの保温器を使っていると、ケージの中が乾燥しがちになります。濡れタオルなどをして、湿度が50%を下回らないように注意してください。
窓の開閉
文鳥は窓が開いていると逃亡することがあります。外に出てしまえば、自力で帰ってくることが困難です。ケージの外に出す時は、部屋の窓を必ず確認しましょう。また、レースカーテンは爪に引っかかりやすいので束ねておきましょう。
ほかのペットの攻撃
ほかのペットに攻撃されないように注意が必要です。犬や猫はもちろんですが、ハムスターもケージの隙間から文鳥を攻撃することがあります。ウサギは攻撃しないので安心ですが、金魚などの水槽は文鳥が落下事故を起こす可能性もあるので、ふた付きのものにしましょう。
毎日のお世話
文鳥は1日エサを食べないと死んでしまうことがあります。毎日のお世話が必要な生き物なので、旅行などで不在の際は、代わりにお世話をしてくれる人の手配を忘れないでください。
また、人との適度なコミュニケーションがないと、文鳥は人を怖がるようになります。少しでもケージから出して、遊ぶ時間をもうけましょう。
また文鳥を飼う時に絶対にやってはいけないことがあります。それは「マニュキア・ボンド・ペンキ・シンナー」などの有機溶剤系のにおいで死んでしまうことがあります。
そのため、ヒーターやカバーなど、文鳥に使う物も新品はしばらくにおいを取ってから使用することをおすすめします。
病気
文鳥の病気には「そのう炎・肝臓の病気・皮膚の病気・結膜炎」が挙げられます。そのう炎と肝臓の病気が起こる原因として、「細菌や過剰な食事・合わない食べ物」により起こりやすくなります。
皮膚の病気は、文鳥特有の糸状菌というものが繁殖して、皮膚に異変が起こります。予防策としては飼育環境をキレイにして飼いましょう。結膜炎は、何が擦れたり、目が傷つくと起こりやすくなります。涙目や赤みがあるなどしたら、病院で診てもらいましょう。
飼育時に気をつけるポイントは以上となります。文鳥とコミュニケーションをとっていいれば急な変化にも気付きやすいので、普段からスキンシップをとるよう心がけておくことが大事です。
文鳥がなつく方法は?

「手乗り文鳥」という言葉を聞いたことがありますか?
文鳥は飼い主に懐きやすく、ペットとしても人気があります。しかし中には懐いてくれない、育ててるのは私なのに他の家族に懐いている…なんて声をも聞きます。ではどうしたら文鳥が懐いてくれるのか?そのコツをお教えします。
文鳥の懐かせ方 【雛から育てた場合】
まず雛から育てた場合だと、文鳥が非常に懐きやすくなります。
雛は警戒心が少なく、育ててくれる人を親やパートナーだと思ってくれます。特に大切な時期は雛から大人の羽に替わる換羽期の時期になります。その時に飼い主への評価が大体決まります。
しかしちゃんと餌を与えたりお世話をしていれば、自然と心は開いてくれるでしょう。
文鳥の懐かせ方 【成鳥から育てる場合】
次に成鳥してから懐いてもらう方法ですが、まずは話しかけたりケージから放鳥する時間をとりましょう。狭いケージの中はストレスも溜まりやすいです。運動不足の解消も兼ね、スキンシップをとる時間にもなるので遊んであげましょう。
初めの頃はひとりで遊んだりもしていますが、放鳥を繰り返しているうちに飼い主の元へと遊びに来るようにもなります。
文鳥は繊細で寂しがりなので、放ってばかりいると懐いてくれるものも懐いてくれません。また構われすぎるのも嫌になってしまう事もあります。この辺りは人間と同じですね!適度な関係を築いていきましょう。
また他にも文鳥がヤキモチを妬いてしまうこともあります。特にメスは嫉妬心が強いので、本当に懐いて欲しい!と考えるのであれば、文鳥は1羽にするのが良いでしょう。反対に文鳥同士が仲良くなりすぎて、飼い主に見向きもしなくなる事もあるようです。
文鳥は賢く、飼い主からの愛情をそのまま返してくれます。なので乱暴にしたり、驚かせたり、怖がらせるなどの文鳥にとって嫌なことをしてしまうと警戒され、側にすら寄ってこなくなります。
特に「手乗り文鳥をしたい!」と躍起になって無理やり捕まえて手の上に乗せることをしていると、文鳥からも警戒されて嫌われてしまいます。手乗り文鳥をするのにもちょっとしたコツがあるので、段階を踏んでいくことが大切です。
手乗りにさせたいならまずケージ越しに餌をあげる、手から直接食べさせる等して徐々に警戒を解いてあげることが大切です。
そうしていくうちに徐々に腕に止まるようになり、手に止まるようになり、指に止まるようになれば成功です!なので、初めから手に乗ってくれる事を期待してはいけません。
文鳥の可愛さあまりに焦ってしまわないよう、徐々に文鳥からの信頼を得ることが懐いてくれるポイントになります。
文鳥は飼育に手間がかからないからこそ、そういった普段からの関わり方を大切にして育てていきましょう。
文鳥の鳴き声について

文鳥の鳴き声って綺麗で癒されますね…実はその鳴き声に意味がある事をご存知ですか?しかもその意味が分かるともっと飼育が楽しくなります。
文鳥の鳴き方は非常にバリエーションが豊富ですが、ここでは1番よく耳にする鳴き声について解説してきます。
呼び鳴き
まず【呼び鳴き】といわれるものですが、「ピッ!」「ピッピっ!」と短く鳴くものです。
これは文鳥が飼い主に何かして欲しいときにそういった鳴き方をします。例えばケージから出して欲しいときや、構って欲しいときに「ねえ、ねえ、飼い主さん!」と呼びかけているんでしょう。聞いてあげるまで鳴き続けることもあるので、早めに気付いてあげましょう。
不満な時
文鳥にも、もちろん不機嫌なときもあります。そんなときは「ギャッギャッ」と低めの声で鳴きます。
ご機嫌が良さそうだったのに、この鳴き方に変わったら何か不満があるのでしょう。例えばもっと飼い主さんと遊びたかった時にご機嫌が斜めになってしまうという事もあります。
しかし、ここまではまだ大丈夫ですが、更に鳴き方が変わったら注意が必要です。
「キャルルル」、「ギャルル」などと鳴いたときは「威嚇」に変わっています。つまり怒っているのです。周囲に危険が迫っている時もこのように鳴きます。
この鳴き方の時は文鳥も普段の可愛い様子から豹変して怒りを表に出します。突いてきたり噛んだりすることもあるので注意しましょう。
挨拶
挨拶は「ピピピ」「チチチ」と長めに鳴きます。
起きた時や、仕事から帰ってきたときなどに鳴いてくれます。また、文鳥を2羽以上飼育していると、それぞれの鳴き方が交じり合って更に綺麗な鳴き声になったりもします。
オスから聞く事の出来る鳴き声はやはり「求愛」でしょう。「ピチューィ」「ピーヨ」と鳴いて、体を膨張させて、ぴょんぴょんと跳ねるようにダンスをしながら鳴いてくれます。発情しているときにはもちろん鳴きますが、飼い主に甘えたいときにも鳴いたりもします。
また「キュゥゥゥ」と鳴くのも文鳥が甘えたいサインです。突然鳴き始めたら、寂しがっているので遊んであげましょう。時間があるときは放鳥してあげると良いですね。
簡単に書きましたが、他にも文鳥はいろんな鳴き方をするので一概には言えないところが大きいです。しかし飼育しているうちに、飼い主さんにはその意味をなんとなく分かってくるそうです。
寂しいときに鳴く鳴き方、威嚇する鳴き方、求愛、と全ての文鳥が同じようには鳴きません。それぞれ癖があるので、普段からしっかり文鳥とコミュニケーションをとってあげることが大切です。
文鳥の爪切りについて

文鳥のお世話の中で1番手がかかるのが「爪切り」です。初めての爪切りは飼い主も文鳥もどちらも不安ですよね。しかし野生と違ってペットは爪が自然と削れにくく、どんどん伸びてきてしまいます。
最近ではやすりをつけた止まり木もあり、削れるような工夫がされた商品も開発されていますが、文鳥はクチバシをこすりつけてしまう事もあるので結局は飼い主が爪切りをしてあげる方が多いです。
爪が長いと止まり木などを掴み辛くなりますし、ケガにも繋がるので定期的に爪切りは必要です。
用意する爪切りですが、これはペット用のものでも人間用のものでも大丈夫です。小さめのものが使いやすいのでオススメです。
爪が伸びてくると白い部分が内側にむかって、くるんっと巻き上がってきています。
これを切っていくのですが、文鳥はじっとはしてくれないので「保定」と呼ばれる掴み方をします。具体的には、人差指と中指で文鳥の首の根あたりをはさんで、それ以外の指で体を押さえてあげます。文鳥は何をされるんだろう…と怖がってもがいてしまうため、抜けないようにする持ち方です。しかし爪切り中は大人しくなってくれることはあまりない為、何度も「保定」を繰り返すことになります。
焦って首を締め付けすぎたり、強く握ってしまうと危険なので、一旦逃がしてあげるなどして根気よく頑張りましょう。
「保定」が出来たら、爪を固定します。爪には血管が通っているので切りすぎてしまうと血が出てしまいます。切るラインとしては薄く血管が見えているので、そこから1mm程度あけると良いでしょう。万が一出血してしまったら、少しだとそれほど問題はないですが、止血処置が必要なレベルになってしまうと、線香で焼いてあげると一瞬で止血できます。痛そうに聞こえますが、爪には神経は通っていないので文鳥も痛みは感じません。しかし失敗して二次被害が怖い…という方には他の止血方法もあります。止血粉や小麦粉を塗っても止血できます。どれだけ気を付けて爪切りをしていても出血はしてしまうので、対処方法は頭に入れておくと良いですね。
爪の切り方の角度ですが、少し斜めに切ってあげると良いでしょう。直角に切ってしまうと地面に立ったときに浮いてしまいます。斜めに切ると接地面と平行になるので、爪切りに慣れてきたらベストな角度が分かってくるでしょう。
以上が文鳥の爪切りになりますが、中には極端に爪切りを嫌がる子もいるので自分の文鳥がそうだったら頭にハンカチやガーゼで覆ってあげるのも1つの手です。爪切りは最初はする方も怖いですが、慣れなので頑張りましょう!
文鳥を飼っている私の実体験

ここからは白文鳥を飼っている私の意見を元に、文鳥の特徴について紹介していきます。
私は白文鳥のメスを1匹飼育していますが、その白文鳥は家族の中で娘にとても慣れていています。
私がゲージの掃除などをすると怒り出すことがありますが、娘にはまったく怒ることや、つつくこともなく安心した表情でリラックスしています。
卵詰まりで辛そうにしていた時も、娘の手のひらで卵を産んでしまうこともあるくらい、単独飼育だと一人に対してとても懐きやすく信頼感が強いです。
卵といえばメスは、無精卵の卵をよく産みます。
なるべく体に負担をかけないようにしたいのですが、自分で下の新聞紙をちぎり巣作りしてしまい、冬と秋は体調を崩しやすい面、落ち着かず鳴く頻度も高くなります。でも夜中は一年通してとても静かです。
産んだ卵は暫くゲージに入れておき、卵を暖める行動などはしません。
文鳥は年を取ると、賢くなるといわれています、5年目・・・最近は餌箱の下のすき間が落ち着くのかゆっくりする姿も見られますが、名前を呼ぶとすぐに反応してくれ、止まり木にとまり姿を見せてくれます。
歌をうたうと、一緒に歌ってくれるなど、家族のムードメーカー的存在で、今では大切な一員としてとても可愛いです。
我が家はマンションなので小動物しか買えませんが、文鳥は掃除も楽だし、餌代も低価格なので飼育しやすいです。
寿命も長いのでそのぶん愛着も沸くので、亡くなってしまった時のことを考えるととてもさみしいですが。
娘のお友達の白文鳥は、もっと大人しく誰の手のひらの中でもすぐにおもちになり、鼻の穴をすぐにつつくそうです(笑)
10月24日は文鳥の日って知っていましたか?
実は10月24日は文鳥の日と制定されているんです。これは文鳥に詳しい伊藤美代子さんが制定したとのこと。
どうして10月24日なのかは、「て(10)に(2)し(4)あわせ」(手に幸せ)と読む語呂合わせと、この時期が手乗り文鳥のヒナが出回ることから10月24日を文鳥の日と制定したみたいです。
ちなみにこの記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されているんですよ。
文鳥を飼っている人や文鳥好きな人は10月24日は何かしらお祝い事をしてみてはいかがでしょうか?
まとめ
文鳥は人懐っこくてホント愛着が湧くペットです。
ペットの中でも飼いやすい部類なので、初めてのペットに文鳥はおすすめです。ただ文鳥も生き物ですので、飼うと決めたからには最後まで責任もってお世話をすることだけは忘れないようにしましょう。
家庭用ペット(鳥類)の中で人馴れがよく、ヒナから育てると手乗りもしてくれることで人気のキンカチョウ。 ペットをあまり飼っていない人には聞き慣れない鳥かもしれませんが、愛くるしい表情と小さいサイズに癒やされる人も多い動物です。 そんな愛ら[…]
家庭用ペット(鳥類)の中では比較的おとなしく優しい性格で飼いやすいさが魅力の「十姉妹」。 サイズも小さく愛らしい可愛さや同一ケージ内での多頭飼育が可能など、十姉妹の魅了され飼いたいと思う人も多いと思いますが、ただ実際に飼うとなれば必要なモ[…]