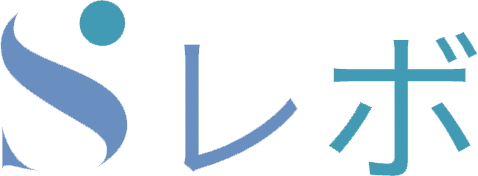みなさん「クチボソ」というお魚をご存でしょうか?よくモロコと一緒にされがちな魚なのですが、観賞魚として勝っている方もいるのではないでしょうか。
今回はクチボソとモロコとの違いや、クチボソを家庭で飼う時に知っておきたい情報をまとめました。
クチボソとモロコとの違いについて

まず、クチボソとモロコの基本的な情報を見ていきます。
【クチボソ】
クチボソはモツゴとも呼ばれており、地方によって色々な呼び名があります。
| 体長 | 8㎝~11㎝ |
|---|---|
| 特徴 | 体色は銀白色で、鱗が黒くはっきりしており、名前の通り口が細く上向きについています。 |
| 生息 | 湖沼、河川、公園の池などにも生息し、水質が悪化している場所への適応力も高いため、色々なところで見られる魚です。水草が豊富で、流れの緩やかな浅底部に群れて生活するのが特徴です。 |
【モロコ】
モロコには「諸々の子」の意味があり、体の細長い小魚にこの名のつくことが多いです。単にモロコという和名の魚はいませんが、クチボソ同様、地方によって色々な呼び名があります。モロコも地方名で、正式名称はタモロコと言います。
| 体長 | 6㎝~15㎝ |
|---|---|
| 特徴 | 全体的に体が丸っぽく、口にはヒゲがあり、体の中心に少しぼやけた黒い線があります。ただ、ヒゲをもたない小形の淡水魚にもモロコと付けて呼ぶ場合もあります。 |
| 生息 | 元々は琵琶湖の固有種とされていましたが、最近は、山梨県の山中湖、長野県の諏訪湖、東京都の奥多摩湖などでも移植され見られるようになりました。 |
以上の事を踏まえて、モロコとモツゴの見分け方を説明していきます。
見た目の違いは?
クチボソは、体色が銀白色で、黒い側線(体の側面に入る線)がはっきりと眼をから口先まで続いています。この黒い側線は、成長に伴って薄くなっていく個体もいます。
また、繁殖期(4~8月)にオスは婚姻色で体が黒くなり、黒い側線が見えなくなります。メスは、腹部が膨らみます。
※婚姻色とは
魚類や両生類、爬虫類、鳥類などの一部の動物で繁殖期に現れる平常時とは異なった体色や模様のことをいいます。魚類では多くの魚で婚姻色が見られ、派手な色の婚姻色の魚が多いです。繁殖期には、婚姻色の他に「追星」(おいぼし)と呼ばれる、ブツブツとした白斑が現れる種もいます。
普段は、オスとメスの見分けが難しいクチボソも繁殖期には、見分けがつきやすくなります。口はおちょぼ口か受け口です。(クチボソと言われるのは、このためです。)
モロコは、体色が白っぽく側線(体の側面に入る線)がエラか目の前まで伸びており、口がコイのように大きく開いています。口にはヒゲがあるところも、クチボソと違います。(一部種類に口ヒゲがない場合もあります。)養殖について
埼玉県などで「ざこ煮」と呼ばれ、クチボソを食べる習慣がありましたが、河川の水質悪化、クチボソの一度に大量の卵が得にくいという事情により、今ではモロコの養殖のほうがさかんに行われています。
元々は琵琶湖にいたモロコですが、今では埼玉県などで盛んに養殖が行われ、食用として流通しています。
クチボソの寿命について

クチボソは淡水魚ですが、淡水魚とは日本の河川や沼地、用水路に生息している魚のことを言います。
日本には四季があり、冬には水温が0℃以下になることもあるため、水温適応力が高い生き物ではないと生き残ることが出来ません。
言い換えれば、日本の淡水魚は厳しい環境でも生き抜くことが出来る、とても丈夫な魚たちと言えます。
その中でもクチボソは水温適応力もあり、水質悪化にもある程度適応出来る飼育しやすい魚です。
淡水魚でポピュラーなタナゴやアブラハヤの寿命は、4年前後と言われますが、クチボソも同様に寿命は3年、長くて5年くらいです。
ここでは、クチボソの寿命を延ばすためにどのように飼育してあげるのがよいかポイントをみていきます。
【注意するポイント】
- 水温、水質管理
- エサについて
- ストレス
注意するポイントを細かく見ていきます。
水温、水質管理
クチボソは、水温、水質に適応力が高いと言われているため、神経質にチェックする必要はありません。
ただ水質管理が悪いと、体調悪化や寿命を縮めることに繋がります。
基本的なことですが、飼育時には水温と水質を確認しておくと安心でしょう。
まず水温ですが、クチボソを飼育する適温は5℃~30℃と言われ、適温の幅が広いため必ずヒーターが必要というわけではありません。
ただ夏場、冬場に温度が変化する場合には、クーラーやヒーターで水温を調整してあげることで、クチボソは元気に過ごせるでしょう。
またクチボソは水質への適応力が高いので、pH6.0~7.0の弱酸性から中性の範囲であれば、どんな水質でも飼育できます。
しかし、適正範囲であってもpHが急激に変化すると、魚がショック症状を起こしてしまい、「pHショック」と呼ばれるショック状態に陥ってしまいます。pHショックを防ぐためにも、ペットショップから買ってきた場合など、ゆっくり水槽の水に慣れさせる「水合わせ」を行い、飼育を開始しましょう。
※pH(ペーハー)は、0~14の数値で表され、7が中性、7より小さい数値は酸性、7より大きい数値はアルカリ性となります。日本の水道水の基準値は、pH5.8以上8.6以下です。急激な水質の変化がなければ、水道水で問題ないです。ただ水道水を使用する場合、水道水に含まれる塩素(カルキ)を抜かなくてはいけないため、市販の水質調整剤を使って水づくりをしてあげましょう。
エサについて
クチボソは雑食性の魚で、動物性のエサも植物性のエサも食べるので、どんなエサでも飼育することができます。
基本的にはメダカや金魚の人工餌が簡単ですが、アカムシなどの活餌や、乾燥糸ミミズなども食べます。体調や食いつき具合をチェックして、エサを上げるのがよいでしょう。
また、エサはあげすぎに注意が必要です。エサのあげすぎは水質悪化にも繋がりますし、これが原因でクチボソがエサを食べ過ぎ、消化不良を起こして早死にしてしまうということが考えられます。
どんな魚でもあり得ることですが、適切な頻度と量を与えるのが魚にとって大切です。エサは、1日に2~3回、2~3分で食べきれるくらいの量が適量です。
ストレス
クチボソ以外の種類の魚を飼育するうえでも同じことが言えますが、過密飼育は魚のストレスになり寿命を縮める原因になります。
クチボソは群れで泳ぐ習性があるため、複数匹で飼育する場合、45㎝水槽か60㎝水槽がおすすめです。
飼育をする場合には、いじめられている個体はいないか、調子が悪そうな個体はいないかなど普段から気を付けてあげると、クチボソもストレスなく過ごせます。
追いかけまわしていたり、つついている個体がいる場合、別の水槽に移してあげるほうが、他の個体がストレスなく生活出来ます。
クチボソのエサについて

クチボソは水面でエサを食べる際、小さな口で勢いよく吸い込むためパチパチと音をたてエサを食べる特徴があります。
クチボソは雑食性の魚で、動物性のエサも植物性のエサも食べるので、どんなエサでも飼育することができます。基本的には人工餌が簡単ですが、ここでは具体的にどんなエサがあるか見ていきます。
川魚のエサ
ペットショップや、アクアショップなどで手軽に購入出来ます。
日本に生息する淡水魚に合わせた専用飼料なので、クチボソにもおすすめです。タナゴ、モツゴ、ドジョウ、フナなどの淡水魚に適して作られています。
沈下性(水に沈むエサ)でも、浮遊性(水に浮くエサ)でもどちらのエサでも食べてくれます。またエサが大きすぎるとクチボソの小さな口で食べづらいので、なるべく小さめの口のサイズにあったエサがよいでしょう。
金魚のエサ
金魚のエサにも沈下性のものと浮遊性のものがありますが、どちらでもよいでしょう。
ゆっくり沈下するタイプのエサは、クチボソもエサを食べやすいというメリットがありますが、浮遊性のエサは、食べ残しがあった場合エサをすくってあげることで水槽内が汚れないというメリットがあります。
エサの形は、顆粒タイプやフレークタイプがあります。
メダカのエサ
メダカのエサは100均でも購入出来ますが、アクアショップなどでも安く購入出来るので、色々なタイプをチェックしてから購入したほうがよいでしょう。
メダカのエサには顆粒タイプ、フレークタイプなどありますが、どんなエサをあげていいか迷う場合は、顆粒タイプが安価でおすすめです。飼育に慣れてきたら、色々なエサをあげてみましょう。
糸ミミズ(フリーズドライタイプ)
糸ミミズを乾燥させ、ブロック状に四角く固まらせているエサです。
このエサは浮遊性で、エサに気付いたクチボソが集まってきて、パチパチ音をたてて、エサを食べる姿が見られるはずです。すぐには沈まないので、時間が経って食べ残しや食べカスが水面上にあったらきれいにすくってあげることで、水槽内が汚れません。
乾燥アカムシ
アカムシを乾燥したタイプで、基本は活餌のアカムシと変わりませんが、ビタミンが添加されていたり、殺菌されているものも多くあるので成分表などをチェックして購入するのがおすすめです。
活餌
アカムシ、糸ミミズ、ミジンコなどを加工しない状態で与えることを活餌と言います。
食いつきがよく、クチボソもよく食べてくれますが、管理が大変なので、上記の人工飼料や乾燥タイプのエサと合わせて用意するのが、おすすめです。
エサの与え方
クチボソは、エサをよくたべます。
特に春〜秋にかけては比較的よく食べるため、エサは多めに与えるようにします。1日2〜3回、数分で食べきる量を与えます。
クチボソの飼育に必要なもの

飼育に必要なものは主に7点です。
- 水槽
- ろ過フィルター
- 底床
- ライト(水草を設置する場合)
- 水温計
- エサ
- 水質調整剤
飼育に必要なものを、細かく見ていきます。
水槽
クチボソは群れで泳ぐことが多い魚です。そのため単体で飼育するよりも、複数匹で飼育するほうがおすすめです。クチボソの数に応じて、水槽のサイズも変えたほうがよいでしょう。複数匹で飼育する場合は、45㎝水槽以上が理想的です。
クチボソは、淡水魚の中では水質悪化に適応出来る魚ですが、小型水槽での過密飼育は、水質悪化による体調不良になってしまうことが多いので、注意が必要です。
ろ過フィルター
ろ過フィルターは、水槽の水を循環させ、水の汚れを分解してきれいな水を作ってくれます。ろ材の部分にバクテリアが繁殖すると、水質が安定します。バクテリアの増殖には最低でも2週間、長くて2ヶ月程度かかるので水質が安定するまでは、水質に注意して飼育が必要です。
クチボソは水質悪化に強い魚なので、ろ過フィルターはなくても飼育可能です。ただ飼育数が多い場合など、水質悪化が原因で体調不良になることがあるので、ろ過フィルターは、付けておいたほうがよいでしょう。
底床
底床を敷くことの最大のメリットは、バクテリアの繁殖を促すことです。バクテリアが繁殖することで、食べ残したエサやフンなどを目立たなくしてくれると同時に有害物質を分解し、水槽内の水質を安定させてくれます。
クチボソを飼育する時の底床は、特にどの種類の底床でも問題ありませんが、吸着タイプのソイルなどがおすすめです。吸着ソイルは、クチボソの排泄物なども吸着してくれるので、水質向上にも役立ちます。また、細かい小石が混ざったいわゆる砂利の「大磯砂」、細かいくて丸い粒の「田砂」などがおすすめです。
ライト
クチボソにとってライトは必要なものではないですが、水草を入れている場合は、ライトを入れなければ光合成できず枯れてしまうので、ライトの設置が必要になってきます。
水草はクチボソの隠れ家になるので、入れてあげた方がストレス軽減になります。
水温計
水温に適応力があるクチボソは、水温管理は重要ではありませんが、水温のチェックは、クチボソの体調管理にも繋がるので水温計があったほうがよいでしょう。クチボソに最適な水温は、5℃~30℃です。
エサ
クチボソは雑食性の魚で、動物性のエサも植物性のエサも食べます。淡水魚用のエサや金魚のエサなど、アクアショップやペットショップなどで購入出来るのでおすすめです。基本的には人工餌が簡単ですが、メダカなどと混泳して飼育している場合、メダカのエサでも飼育可能です。
水質調整剤
水質調整剤を使用し、水道水に含まれる塩素(カルキ)を取り除き、クチボソの飼育に適した水にします。一般的に、どんな魚でも飼育する前に水のカルキ抜きが必要です。
使用方法は、水道水を入れたバケツに水質調整剤を規定量を入れ、よくかき混ぜて使用します。特にクチボソ用というものはなく、熱帯魚用や金魚用として販売されているものでOKです。
水槽に水を入れる2日くらい前に、水をバケツに入れておくことで水質調整剤を使用しなくとも、カルキ抜きが出来ます。これはクチボソに限らず、どんな魚にも有効な方法ですが、時間がない時などは、水質調整剤を使用するのが簡単です。
飼育で気をつけるポイント

クチボソを家庭で飼育する際に注意するポイントが以下です。
- 水温、水質管理
- 繁殖について
- 混泳について
注意するポイントを細かく見ていきます。
水温、水質管理
クチボソを飼育する適温は5℃~30℃と言われており、特に水温管理に気を使う種類ではなく飼育が簡単な魚です。
ただ、夏場など30℃を越える場合はクーラーなどで水温を下げたり、冬場の水温が5℃を下回る場合は、部屋の温度をヒーターなどで温めて水温管理をしましょう。
クチボソは適応力の高い魚なので、水質を神経質に調整する必要はありませんが、適した水質は、弱酸性~中性と言われています。pHであれば6.0~7.0くらいであれば、クチボソは飼育可能ということです。
※pH(ペーハー)は、0~14の数値で表され、7が中性、7より小さい数値は酸性、7より大きい数値はアルカリ性となります。
基本的に、日本の水道水の基準値はpH5.8以上8.6以下です。急激な水質の変化がなければ、水道水で問題ないということです。ただ水道水を使用する場合、水道水に含まれる塩素(カルキ)を抜かなくてはいけないため、市販の水質調整剤を使って水づくりをしてあげましょう。
繁殖について
クチボソの繁殖期は4月~8月頃です。繁殖期になると、オスは縄張りを主張し攻撃的になります。またオスは婚姻色で体が黒くなり黒い側線が見えなくなり、追星(おいぼし)と呼ばれる白い斑点がエラの周りに現れます。メスは、腹部が膨らみます。
※婚姻色とは
魚類や両生類、爬虫類、鳥類などの一部の動物で繁殖期に現れる平常時とは異なった体色や模様のことをいいます。魚類では多くの魚で婚姻色が見られ、派手な色の婚姻色の魚が多いです。繁殖期には、婚姻色の他に「追星」(おいぼし)と呼ばれる、ブツブツとした白斑が現れる種もいます。
注意点としては、繁殖期にオスが攻撃的になるので、混泳させている場合など他の魚を攻撃していないか観察し、追いかけ回したり、つついたりしているようなら別の水槽に離隔して飼育するほうがよいでしょう。
混泳について
クチボソは温厚でおとなしい性格なので、同じサイズくらいの淡水魚と混泳可能です。また群れで泳ぐ習性があるので、複数匹で飼育も可能です。その場合に注意することは、過密飼育と水質管理です。
クチボソは丈夫で飼育しやすい魚ですが、狭すぎる水槽や隠れ家がない場合などストレスになってしまいます。ストレスを多く感じると、エサを食べなくなり体調不良になってしまいます。水槽は出来れば大きめの、45㎝水槽か60㎝水槽がよいでしょう。また、水槽内に水草や石などを設置してあげることで、隠れ家になるのでストレス軽減になります。
水質ですが、クチボソは水質に適応力がある魚なので、常に水質を管理する必要はありませんが、過密飼育とエサのあげすぎなどが水質悪化に繋がります。水質悪化がひどい場合は、ろ過装置の設置、水換えなどで管理してあげましょう。