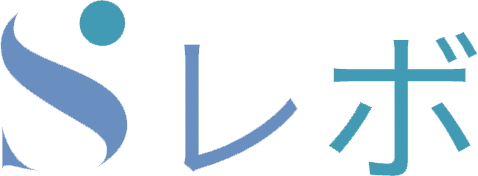ニワトリの一種で家庭用ペットというより食用のイメージが強い「チャボ」ですが、実際に飼うことができるのを知っていますか?ただ通常のホームセンターやペットショップではほとんど販売されていないので、今回はチャボを飼育する時に気をつけるポイントやチャボの種類・値段についてまとめてました。
チャボの生態について

卵は普通のニワトリと比べて非常に少なく、年間に90個ほどしか産みません。抱卵が好きで、他の鳥の卵も抱卵します。抱卵しない鳥種の仮母として重宝されることがあります。強いオスのリーダーを中心とした社会生活を営みます。しかし、オスが多いとボスでの争いが多くなるためオスは少なめが好ましいです。声はニワトリに比べたら小さいですが、雄叫びは声が大きいため、少々防音対策が必要になります。
ニワトリもそうですが、チャボにも立派な鶏冠があります。この鶏冠のある意味としては、メスへのアピールと言われています。オスの鶏冠はメスのものよりも立派なことから、メスの注目を集めているのかもしれません。また、クチバシの下にぶらさがっている「肉垂れ」の存在ですが、これがある意味として、鶏冠や肉垂れで体温を調整しているという説があります。鶏冠が肉質なことから放熱するためで、熱に弱い脳を守るためだと考えられます。また、鶏冠は体調の変化がすぐあらわれます。鶏冠が垂れてしまったり、色が変わってしまったりした場合はどこか体調が悪い可能性があるため、病院に連れて行くことが望ましいです。
ニワトリが怖いという方が多いですが、チャボは体長が20㎝と小さく、手のひらに乗せることもできる大きさです。オスの特徴として、立派な鶏冠・尾羽・肉垂れ・蹴爪があり、朝は大きな声で鳴きます。メスはオスより鶏冠などが小さめです。オスほどではないですが、メスも時々鳴きます。寿命は7〜10年です。体重はオスが約730g、メスが約610gです。性格も温厚なため、人に攻撃する子は少ないです。また、観賞用として改良された品種のため、見た目がとてもキレイで足が短く、ポテポテと歩く姿が可愛らしいです。産まれた時から人に育てられることにより、人を警戒しないため、人になつきやすくなります。日本では天然記念物に指定されています。
チャボの飼育に必要なもの

まずは、ケージまたは飼育小屋です。何羽飼うかにもよりますが、1羽であれば犬用犬舎やうさぎのケージで大丈夫です。大きさでいうとだいたい、縦67㎝・横52㎝・高さ60㎝の大きさが好ましいです。
また、複数飼う場合は3羽で最低4畳くらい必要です。ただし、オスを一緒に2羽飼うことは、エサを取り合ってしまうので、オススメしません。飼育は屋内外どちらでも可能です。
屋内で飼う場合は1日に最低2・3時間放鳥してあげてください。屋外の場合は、広めのケージを用意し、高さのあるものにします。高いところに止まって休む習性があるため、止まり木を設置してあげるといいでしょう。
他の動物にケージを壊されないように、頑丈で目の細かいものにしましょう。飼育小屋は南東または南向きに設置し、西日や直射日光がはいらないようにします。
次に餌です。チャボの主食はトウモロコシを始めとする穀物を主原料に配合されたものです。メスは、卵を産むためカルシウムを多く必要とします。なので、カルシウムが多く配合された餌を与えます。
副食として、キャベツなどの葉物を中心とした野菜(キャベツ・小松菜・チンゲン菜・レタス・カボチャ・ニンジン・ブロッコリー・リンゴなど)を細かくきざんであげると喜びます。
ただし、生のほうれん草・セロリはシュウ酸が強く、カルシウムと結合して多く摂取するとカルシウム欠乏を起こしやすいので避けましょう。餌や水は毎日新鮮なものをあげます。
あとは、ヒヨコから飼う場合は温度管理が必要です。ヒヨコは非常に低温に弱いので、ヒーターなどを使い温めてあげます。
ケージを発泡スチロールや段ボールなど保温性があるものでかこって、昼夜の寒暖差をつくらないようにします。体が濡れてしまうとすぐに弱ってしまいます。水入れはこぼれにくいものにします。
チャボの種類について

チャボは、ニワトリの中でも小型で、脚は短く、尾羽が直立しているのが特徴の美しい鳥で、江戸時代頃から観賞用として愛されてきました。1941年に日本の天然記念物に指定されています。
現在のベトナム中部沿海地方存在し、当時日本と交流のあった「チャンパ王国」から日本にやってきたと言われていて、その後改良が進み現在の姿になっています。
チャボはニワトリの中でも、とてもおとなしい性格で、比較的狭い場所でも飼育が可能なためファンも多い鳥ですが、鳴き声の問題で飼育されることが減り、絶滅が心配される種類もあります。
天然記念物に指定されているチャボは25品種存在し、実際に飼育されている種類はもっと少なくなっています。
とさか、羽毛、羽色などの違いで多くの品種に分けられていますが、色は主にオスの特徴で、メスには該当しない場合があります。
美しい姿で海外にもファンの多い、チャボの人気の種類をご紹介します。
桂(かつら)
全体が白い羽毛で、尾に黒い色が入っているのが特徴です。
しろ
全身が雪のようにまっ白で、とさかや顔、目の下のほうにある耳も赤くなっています。
くろ
全身が黒い羽毛で覆われているのが特徴です。
真黒(しんくろ)
全身が黒い羽毛で、とさかまで黒い種類です。
碁石(ごいし)
白い羽毛と黒い羽毛がまだら模様になっていて、碁石のように見えるのが特徴です。
桜碁石(さくらごいし)
白い羽毛と薄い茶色の羽毛がまだら模様になっています。
三色碁石(みいろごいし)
白と薄い茶色、黒三色の羽毛がまだら模様になっています。
浅黄(あさぎ)
全体が濃いグレーの種類です。
猩々(しょうじょう)
全体が茶色で、尾に黒い色が入っているのが特徴です。
淡毛猩々(うすげしょうじょう)
全体が茶色で、尾に白い色が入っているのが特徴です。
金鈴波(きんすず)
全体の色はクリーム色を基調としていて、うろこ状で淡褐色の斑が入っています。
銀笹(ぎんざさ)
頭、首、背羽は銀白色で、各羽の中央に黒い線が入っています。尾やお腹の部分は鮮やかな緑黒色になっています。
逆毛(さかげ)
全体の羽毛が逆立っていて、ふわふわしています。
糸毛(いとげ)
全体の羽毛が糸状の羽毛になっています。
翁(おきな)
肉垂(頬や顎の部分の肉質の隆起)が羽毛に覆われています。他の品種は露出しています。
大冠(たいかん)
とさかと肉垂が大きな種類です。
達磨(だるま)
とさかと肉垂が大きな種類で、尾羽が短い種類です。
チャボの値段について

チャボとはニワトリの品種です。日本では天然記念物に指定されています。そのチャボですが値段がいくらくらいになるのでしょうか?気になったので調べてみました。
ペット用ニワトリのチャボ。日本では天然記念物に指定されています。古来よりペットとして愛されていて、愛好家からは根強い人気があります。
そのチャボですが値段はいくらなのでしょうか。オスやメスやひよこで値段がちがうと思うのですが、気になったので調べてみました。
ペットショップやホームセンターはどうでしょうか?カインズホームのペッツワンの公式サイトで調べてみましたが、チャボは売っていませんでした。
大手ペットショップのCoo&RIKUはどうでしょうか…ここでもチャボは売っていませんでした。
それではチャボは値段はいくらなのでしょうか。今回は佐賀県にある「ピーチクパレス」の公式サイトを参考に値段を調べてみました。
| 白チャボ(ペア) | 8,000~12,000円 |
|---|---|
| 桂チャボ(ペア) | 8,000~12,000円 |
| 糸毛白チャボ(ペア) | 8,000~12,000円 |
| 白笹チャボ(ペア) | 8,000~12,000円 |
| 猩々チャボ(ペア) | 8,000~12,000円 |
| 桜碁石チャボ(ペア) | 10,000~15,000円 |
| 銀スズナミチャボ(ペア) | 10,000~15,000円 |
| 真黒チャボ(ペア) | 10,000~15,000円 |
| 銀笹チャボ(ペア) | 10,000~15,000円 |
| 金笹チャボ(ペア) | 10,000~15,000円 |
| 翁白チャボ(ペア) | 10,000~15,000円 |
| 逆毛チャボ 銀笹・黒(ペア) | 12,000~18,000円 |
| 金スズナミチャボ(ペア) | 12,000~18,000円 |
| 3色碁石チャボ(ペア) | 12,000~18,000円 |
※個体の価格は品質や仕入れ状況で変動します。
参考URL【ピーチクパレス】2021年4月30日現在
同じ種類でも羽色、羽質、冠型、尾型、のちがいがあります。
参考URL【全日本チャボ保存協会】:http://www.zennihonchabo.com/
※2021年4月28日現在は新型コロナの影響で仕入れが困難になり、オスとメスのペアでの販売になるそうです。
チャボのひよこは現在取り扱いはないようでした。
チャボの値段はペアで8,000円〜18,000円の間です。チャボは、羽色、羽質、冠型、尾型、のちがい(内種)で値段が変わります。
チャボのオスやメスのみ、ひよこの販売はしていませんでした。
現在、新型コロナの影響でチャボの仕入れが困難になり、販売は繁殖しているところだけでした。ホームセンターやペットショップの公式サイトでは販売されていませんでした。
チャボの飼育で注意する点

チャボはその毛色の美しさからコレクターとして飼われている方もいる知る人ぞ知る人気のペットです。そんなチャボですが、室内でも飼育することは可能です。しかし室内、野外と飼育にはそれぞれ注意する点がいくつかあります。
室内で飼う場合
まずが室内で飼われる場合ですが、大きめのゲージが必要になります。チャボは飛び上がることもあるので、ある程度高さのあるものが望ましいです。運動不足を解消する為、ゲージから出すことも考慮しなければなりません。
チャボにはトイレのしつけは難しく、どこでもしてしまうのである程度は覚悟が必要です。しかし、チャボぼ糞はそれほどニオイがなく、コロコロとした形状をしているので比較的お掃除は楽な鳥類に分類されます。
また高いところで休む習性があるので、止まり木などがなければ自らカーテンレールの上で休むこともあるでしょう。
室内飼いで外になかなか連れ出すことができない飼い主さんは、餌にも気を遣ってあげなければなりません。
チャボは餌を飲んで、砂を食べることによって胃の中ですりつぶす習性があります。自力で砂を食べられないので、小鳥用の焼き砂を適度に与えてあげる必要があります。
野外で飼う場合
次に野外で飼育する場合ですが、注意すべきは外敵がいること。ヘビやカラス、猫などに襲われる可能性があります。
進入したり壊されたりすることもあるので、頑丈で網目の細かなものが良いですね。飲み水なども腐りやすいので、取替えを怠らないよう注意しましょう。
鳥インフルエンザにも注意が必要です。鳥から鳥へと感染するウイルスなので、野鳥と接触しないよう防鳥ネットの準備もしておきましょう。
室内で飼っているからと大丈夫、と過信するのもいけません。鳥インフルエンザは人間には感染はしません。鳥の死骸などに触れウイルスが付着してしまうと、媒介してしまう恐れがあります。
万が一発症が確認されると、高確率で死んでしまいます。そうならないためにも飼い主も気をつけてあげないといけませんね。
複数飼われる場合も、オス同士はクチバシで攻撃し合う、激しい喧嘩をしてしまうこともあります。比較的大人しく喧嘩はしないチャボですが、この組み合わせは避けた方が良いでしょう。
最後にチャボを飼う上で1番気をつけなければならないことですが、チャボは「コケコッコー」と、ニワトリよりも高い声で鳴きます。
毎朝早朝を中心に鳴くので飼育をはじめる前に、後のトラブルに発展しないためにもご近所さんの承諾を得るか、鳴き声に対しての防音対策をしっかりする必要がありそうです。