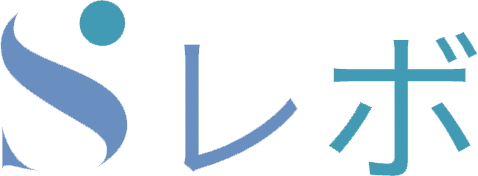動物園やペットショップで大人気の小動物「モルモット」。
家庭で犬や猫を飼うのは難しいけどモルモットなら飼いやすいと思い、飼ってみたいと思っている人も多いのではないでしょうか。
ただモルモットも他の動物と同じ生き物ですので、実際に飼うとなると注意すべきことがあります。
そこでこの記事ではモルモットを飼いたいと思っている人が知りたい疑問について解説しています。
モルモットの値段

モルモットは品種改良によって全く同じ個体がいないといわれるほど、様々な毛色や模様の個体が存在します。そのため、値段も個体ごとにバラバラですが通常品種だと、6,000円前後で販売されている事が多いです。
ただし、珍しい毛色や模様を持った個体になると、通常品種より高い値段で販売されることがほとんどです。
この他にも同じ種類でも購入する場所によって値段が変わってくることがあります。
ここでは値段が変わる違いについて細かく解説していきます。
- 購入する場所による値段の違い
- 「ペットショップ」と「モルモット専門店」での値段の違い
- 種類による値段の違い
- 月齢による値段の違い
主な違いは上記の4点になります。それではそれぞれの値段の違いについて解説していきます。
購入する場所による値段の違い
販売されているお店がペットショップか、モルモット専門店かで値段に違いがあります。
値段が違う理由は「血統がはっきりしているかどうか」、になります。
「ペットショップ」にいるモルモットは親がはっきりしていない混血(ミックス)の子たちが多く、比較的安価であることが多いです。
反対に「モルモット専門店」ではきちんと血統書が付いていて、その子がどのような血を引いているかはっきりわかります。
また、専門店ならではの管理された食事や飼育をしているため、ペットショップより健康な個体が多いです。そのため、一般的には専門店の方が高値で販売されています。
種類による値段の違い
モルモットにはイングリッシュ、アビシニアン、シェルティ、テディ、など色々な種類があります。
中でも特に毛がないスキニーギニアピッグは劣性遺伝子で珍しいため、2万円近い高値となります。
目の色でも違いがあり、黒が優性の遺伝子なので赤い目の子が少なく、そのぶん値段は高くなります。
さらにどの種類のモルモットでもアルビノという全身が白くて赤い目をしている子は、更に高値になる傾向にあります。
月齢による値段の違い
動物を買う時によくあることですが、モルモットも月齢が低く産まれたてに近い子が人気で高値となります。
反対にペットショップで売れ残ってしまった子は、値段が安くなっている傾向があります。
モルモットの種類について

モルモットも小動物の中では比較的種類が多い動物になります。
ここでは日本でよく見るメジャーな種類について解説してきます。
イングリッシュモルモット
別名「ショートモルモット」とも呼ばれ、一般的にもよく見る人気のモルモットです。
毛質は艶のあるサテンタイプとノーマルタイプの2種類がありますが、値段は約2,000円~4,000円程度とお手頃に飼う事がです。
アビシニアンモルモット
「巻き毛モルモット」とも呼ばれ、くせっ毛の強いくりくりした長い巻き毛が特徴的です。
巻き毛が多いものほど希少価値が高いとされていて、値段は約5,000円~7,000円程度です。
クレステッドモルモット
ストレートなタイプと巻き毛タイプの2種類がいる、比較的ポピュラーな品種になります。
イングリッシュモルモットが品種改良された種類で、頭頂部のみにロゼット(つむじのようなもの)があるのが特徴です。アメリカ系とヨーロッパ系に分かれています。
値段は、8,000円~10,000円程度です。
テディモルモット
テディベアのような短い毛が1本1本ねじれるようにカールした縮れた毛を持つことが特徴です。ちなみにツヤのある毛並みを「サテン」と言います。
値段は約8,000円~15,000円程度です。
シェルティモルモット
頭部の毛以外の体毛が美しく、長い毛は品があり高級感を漂わせる人気の種類です。
頻繁に毛のブラッシングとカットが必要な品種です。
値段は約8,000円~12,000円程度です。
ペルビアンモルモット
ストレートなタイプと巻き毛タイプの2種類がいる、比較的ポピュラーな品種です。
しなやかな長毛が特徴で、毛のブラッシングとカットが必要です。
値段は約8,000円~10,000円程度です。
テッセルモルモット
毛はもじゃもじゃに縮れて、ぬいぐるみのような見た目が特徴的です。
値段は約10,000円~15,000円程度です。
スキニーギニアピッグ
体毛がない品種で、ミニブタのような見た目で人気があります。
希少価値が高く、一般の市場ではあまり出回ることがないため、平均的なモルモットよりも高くなる傾向があります。
そのため、値段は約20,000円~40,000円程度とかなり高めな品種です。
最後に種類による値段相場表を記載しておりますので、どの種類を買うか参考にしてみて下さい。
| イングリッシュモルモット | 2,000円~4,000円程度 |
|---|---|
| アビシニアンモルモット | 5,000円~7,000円程度 |
| クレステッドモルモット | 8,000円~10,000円程度 |
| テディモルモット | 8,000円~15,000円程度 |
| シェルティモルモット | 10,000円~15,000円程度 |
| スキニーギニアピッグ | 20,000円~40,000円程度 |
モルモットのエサについて

モルモットは朝夕1日2回エサをあげます。また草食動物なので基本的な主食は以下の3つになります。これと別に清潔な飲み水が必要です。
- 牧草
- 野菜
- ペレット(ペレットは人工的に作られた栄養分が濃縮されている固形のエサです。)
- 飲み水
それではそれぞれ詳しく解説していきます。
牧草
牧草は常に食べられるように、大量に与えておくのがベストです。
牧草はモルモットがよく噛んで食べることで歯が痒いのを解消し、歯が伸びすぎるのを防いでくれます。
モルモットの中には、不正咬合になってしまう個体がいます。
不正咬合とは、噛み合わせが悪いことを意味していますが、前歯が一生伸び続ける「げっ歯類」に属する哺乳類によく見られる症状です。(うさぎやリスなどもげっ歯類です。)
牧草をあげることが不正咬合を防ぐ一番の予防法とも言われているので、積極的にあげましょう。
また繊維質が多いので腸内を正常に保ち、飲み込んでしまった毛を排出してくれることで、毛球症という病気予防にも繋がります。
牧草の種類も2種類あり、成長の過程で与える種類を変えるのがおすすめです。
アルファルファ
マメ科の牧草で高タンパク質、高カルシウムで、生後1年くらいを目安にあげると丈夫な体作りができます。
チモシー
イネ科の牧草で高繊維、低タンパク質なので、大人のモルモットの肥満や膀胱結石の予防に役立ちます。
ペレット
モルモットはビタミンCを体内で生成することができないため、ペレットによって補うのが一般的です。
ただし、ペレットに含まれるビタミンCは空気に触れたり、熱や湿気などによりどんどん破壊され減っていきます。
ペレットが古かったり保存状態が悪いとビタミンCを与えているつもりでも、必要な分を与えられていない事も。
出来ればペレットは、22℃以下で保存して早めに使い切りましょう。
野菜
「小松菜」「大根の葉っぱ」「レタス」「キャベツ」「白菜」「ブロッコリー」「ニンジン」などがモルモットの好物になります。
水分の多い野菜は多く食べすぎると、軟便や下痢になってしまう可能性があるので量を見ながらあげましょう。
食べてはイケない野菜
反対に「ネギ、玉ねぎ、ニラ、じゃがいもの皮と芽、生の豆」などの野菜は与えてはいけません。
またモルモットは野草も食べますが、農薬や殺虫剤、犬のフンなどがついてないか注意する必要があります。
モルモットにあげても良い野草
野草もモルモットは食べることが出来ます。与えていい主な野草が「タンポポ、クローバー、ハコベ、オオバコ、シロツメグサ、ナズナ」などになります。
危険な野草
反対に「アサガオ、水仙、ワラビ、ヨモギ」などは与えてはいけません。※その他、チョコレートやコーヒーもモルモットには有害なエサですので、気をつけましょう。
飲み水
モルモットが飲む水の量は一日100cc~500cc程度です。個体や生育環境によって異なりますが、比較的水を多く飲む動物です。
一日1回もしくは2回水を入れ替えてあげ、雑菌が繁殖し汚れてしまった水をモルモットが飲んでしまうのを防ぎましょう。
モルモットの飼育に必要なものは?

モルモットの飼育に必要なものは以下の7点です。
- ケージ
- 床材
- 巣箱
- 食器(エサ入れ)
- トイレ
- エサ
- 給水器
- その他(かじり木や保温用品、お手入れするもの)
この7点以外にもモルモットの個性に合わせた特別な飼育用品を揃えるといいでしょう。
それでは飼育に必要なものを細かく見ていきます。
ケージ
ケージとは檻やカゴのことで、市販品(プラスチックタイプ)、水槽タイプ、金網タイプなどがあります。
モルモットはジャンプをしないので、30センチほどの壁があれば乗り越えることができません。そのため高さがあるケージを無理に選ぶ必要もないです。
市販品のケージはモルモットのフンが引き出しの中に落ち、引き出しの中を掃除することで清潔が保たれるので便利です。
モルモット専用のケージはあまり多く売られていないため、ウサギ用のケージで飼育する人も多く、他にも衣装ケースなどで自作する人もいるので、飼い主側が自由に決めやすいです。
床材
床材には木のすのこ、紙や新聞紙、チップ、牧草などがあります。
けがの心配をしなくていいのは、新聞紙、チップ、牧草などですが、デメリットとしては汚れやすく掃除の手間がかかります。
ケージの床が網状になっているものは、けがの心配があるので、木のすのこやペットシートを敷いて工夫する飼い主さんもいます。
床材はいくつか試してみて、自分が飼育しやすい床材を選ぶのがよいようです。※またチップはアレルギーになる個体もいるので、注意が必要です。
巣箱
モルモットは、とても臆病な性格なので隠れる場所が必要となります。
ですがモルモット専用の巣箱は少なく、一般的には「小部屋」「ハウス」「シェルター」「巣箱」と呼ばれる市販の小動物用ハウスを購入します。
種類も木製、プラスチック製、牧草製とありますが、基本的にはモルモットの体が隠れて、中で不自由しないようであれば好みで購入するのがよいでしょう。
自分の好みや好きなレイアウト次第で自作するのもよいかもしれません。
モルモットのために、巣箱の中にちぎったわらやティッシュペーパーを入れてあげると喜びます。
食器(エサ入れ)
モルモット専用の食器はあまり売っていないので、ウサギ用の食器を探すのが簡単です。
ケージに取り付けるタイプやプラスチック製、陶器製のエサ入れがありますが、軽いエサ入れはモルモットがひっくり返してしまうので、重さのある陶器製が適しています。
モルモットの頭が入るくらいが食べやすいですが、あまり大きすぎるとモルモットが排泄することもあります。適度な広さと重さのものを用意しましょう。
またモルモットの主食は牧草なので、牧草を入れるケースを用意すると便利です。
トイレ
モルモットはトイレを覚える可能性は少ないです。
ただ、トイレを覚える個体もいるので、設置する場合(小動物用のトイレを購入する。)、モルモットの様子をよく観察して、角や部屋の隅にトイレを設置してあげることで、トイレを覚える可能性があります。
慣れてきてもトイレを覚えなければ、邪魔になるので思い切ってトイレは取り外しましょう。
モルモットは、体の割に排泄物の量が多いです。特に暑いときには、水をたくさん飲み、主に排尿によって体温を下げます。
トイレを覚えなくても、こまめに掃除をして清潔に保ってあげましょう。
エサ
モルモットは草食動物なので、牧草、野菜、ペレットをあげます。
基本的には牧草をあげ、よく噛んで食べてくれることで健康な体が作れます。
またモルモットは、ビタミンCを体内で生成することができないので、ビタミンCが含まれるペレットで栄養を補います。
野菜も好んで食べてくれますが、あげすぎに注意して量を確認しながら与えるのがよいです。
給水器
器に入れ床に置くタイプか、ボトルの給水器に水を入れ、ケージに取り付けるタイプがあります。
床に置くタイプなら、軽いものだとモルモットがひっくり返してしまうので、陶器のものがよいです。
ボトルタイプならモルモットが慣れるまで、きちんと水を飲めているか確認することが大切です。
どちらのタイプも衛生面に注意し、毎日水を取り替えてあげましょう。
その他(かじり木や保温用品、お手入れするもの)
モルモットは基本的におもちゃで遊ぶ習慣はありませんが、かじり木を入れてあげることで前歯が伸びすぎるのを防いだりストレス解消に役立ちます。
冬場の保温用品は、毛布などで保温出来ていれば、ヒーターなど入れてあげる必要はありませんが、「スキニーギニアピッグ」など体毛がない品種は、より寒さを感じやすいです。
必要に応じて、小動物用のヒーターなどを設置してあげましょう。
お手入れは、モルモットの中でも長毛種と呼ばれる毛の長い品種では必須になってきます。
「ブラシ」、「毛をカットするハサミ」、「小動物用のドライシャンプー」など揃えておくと安心です。
これに加え、「ペット用爪切り」を用意すると爪が伸びやすいモルモットの飼育に便利です。
モルモットを飼う時の注意点

実際にモルモットを飼う時には気をつけてあげないといけない注意点がいくつかあります。
飼う前に注意することを知っておくことで、何を買えばいいのか?どう接してあげればいいのかを分かっていた方がモルモットのためにも必要な知識となります。
注意するポイントがこちらになります。
- モルモットの病気
- 温度管理
- ストレス
- 日々のお手入れ
それでは注意するポイントを細かく見ていきます。
モルモットの病気
モルモットも生き物ですので、様々な病気を発症する恐れがあります。主な病気が以下になります。
歯の不正咬合
不正咬合とは、前歯が一生伸び続ける「げっ歯類」に属する哺乳類によく見られる症状で、噛み合わせが悪いことを意味しています。(げっ歯類には、うさぎやリスもいます。)
モルモットは常に伸び続ける常生歯を持っているため、主食である牧草をよく噛んで食べることで歯が摩耗し、歯が伸びすぎるのを防いでいます。
ただ繊維質の少ないエサを食べていると、不正咬合を発症することがあります。
不正咬合になってしまうと、食欲が減退し違う病気にもなりやすく、命にもかかわってきてしまうので、積極的に牧草をあげ、バランスの良い食事でビタミンCを補い、病気を防いであげましょう。
ビタミンC欠乏症
モルモットは体内でビタミンCを合成することができないため、食べ物でビタミンCを補給する必要があります。
毎日のえさで、ビタミンCを含んだペレットかサプリメントを与えることで、ビタミンC欠乏症を防ぐことができます。
ただ、ペレットは長期保存が難しい面があり、いつのまにかビタミンCが劣化・減少してしまい、モルモットは慢性的にビタミンC不足へと陥ってしまうことがあります。
この時、別の原因で体調不良が重なったり、何らかのストレスが加わったりすると、ビタミンCを大量に消費してしまい、その結果、欠乏症を引き起こすことがあります。
毛球症
長毛種の種類に見られる病気で、毛づくろいで飲み込んだ毛が胃に溜まり閉塞してしまう病気です。
毛の長さや形状によりブラッシングを適切に行い、伸びてきた毛をカットしてあげるなどして清潔に保ってあげることでこの病気が防げます。
皮膚病
モルモットの足の裏は毛がなくデリケートなため、傷がついたり、爪の伸びすぎでけがをしたりすることで、傷ができてしまいます。
傷ができ不衛生な床材で飼育していると、細菌が繁殖し皮膚炎になってしまいます。
また劣悪な環境で飼育することで、ストレス、ビタミンCが足りないなどの栄養不足になり、皮膚病を発症することもあります。
温度管理
モルモットの適温は17℃~25℃前後であり、30℃以上10℃以下になると健康を害する恐れがあります。
夏場のモルモットは、水を飲みたくさん排尿することで、体温を下げる習性があります。
ただし暑すぎると水を飲みすぎて下痢になったりすることがあるので、エアコンなどで温度管理をする必要があります。
冬場は長毛種か短毛種かによっても、対応が異なります。特に無毛種のスキニーギニアピッグは、寒さにとても弱いため、小動物用のヒーターを設置してあげることが必須になります。
長毛種は比較的寒さに強いので、エアコン、毛布などで温度を管理し、短毛種で寒さに弱い種類には、毛布や小動物用ヒーターを設置してあげるとよいです。
ストレス
モルモットは体の色々な器官が、微妙なバランスをとり健康を保っています。
そのため過度のストレスで病気になったり、食欲がなくなったりすることがあります。
飼育中のストレスで気を付けなければいけないのは、「大きな物音」、「エサの栄養バランス」、「不衛生な飼育環境」です。
モルモットは警戒心が強い上に、神経質です。
静かな環境で飼育することが理想的です。また、ケージの掃除をこまめに行い、適切なエサを与えることで、病気になる可能性が減ります。
少しのストレスで食事や飲水をしなくなってしまうこともあるため、日々のモルモットの様子を観察して、体調に変化はないかをチェックすることが大切になります。
日々のお手入れ(爪切り、ブラッシングやカット)
モルモットの爪はすぐ伸びてしまうので、伸びすぎると爪が折れてケガをすることがあります。
爪が伸びるのと同時に、爪の中の血管も伸びてきてしまうので、定期的に爪を切ってあげることで、伸びてしまった血管を傷つけ出血するのも防ぎます。
慣れていない場合は、動物病院などで切ってくれるのでプロにお願いしましょう。
ブラッシングやカットは、長毛種と呼ばれる毛の長い品種では必須になってきます。ブラッシングを日常的にしてあげ、清潔に保つことで毛球症などの病気予防にもなります。
モルモットの寿命は?

モルモットの寿命はて4〜8年とバラつきがありますが、平均では5〜6年と言われることが多いです。
ただ最近は社会の進化もや飼育環境の発達により、長生きするモルモットが増えています。
しかも日本でよく飼われているモルモットの種類は小動物の中でも、病気にかかりにくいタイプなので、長生きする可能性が高いです。
とはいえ病気にかからないわけではないので、飼育する際は日頃からモルモットが住みやすい飼育環境を構築することと、飼い主さんが日々状態をチェックすることが大切です。
モルモットの特徴や性格について

動物園やホームセンターなどに必いる人気の動物「モルモット」ですが、どういう性格なのか早速調べてみました。
モルモットの歴史
モルモットは、ネズミの仲間のげっ歯類に分類されます。南米の乾いた高地でモルモットの原種(テンジクネズミ)が生息し、これを家畜化したものが、今ペットとして人気のモルモットと言われています。
モルモットの体の特徴
体長は約20㎝から40㎝、体重750~1200gほどで、頭が大きく足が短いのが特徴で、しっぽが短く丸い体型はペットとして親しまれています。
歯は生涯伸び続ける常生歯と呼ばれ、エサを食べたり、木をかじることで削って長さを保ちます。
モルモットの性格
草食動物特有の温和で臆病な性格ですが、何か求めている時には、仕草や鳴き声で意思表示をするのでコミュニケーションが取り易く、ペットとしてとても飼いやすい動物です。
ただ神経質で警戒心が強く、危険を感じるとすぐに物陰に隠れてしまいます。
モルモットの鳴き声
鳴き声の種類は、個体によって少し違いがありますが、大きな声で「プイプイ」は何かの要求や空腹時、小さい声で「キュルキュル」は甘えている時、 高い声で「キーキーやキュイキュイ」は興奮や怒りを表し、やや低めの声で「グルグル」は何を警戒しています。
慣れてくると、鳴き声の種類で何の意思表示をしているか分かってくるので、メッセージを読み取ってあげましょう。
子供の時の仕草
また、子供のモルモットにポップコーンジャンプと呼ばれる特有のジャンプがあります。
これは楽しい時に見られるとても可愛らしい仕草で、このような仕草からもモルモットがコミュニケーション豊かなのが分かります。
モルモットの行動
モルモットは汗をかけないので、暑いときは水をたくさんのみ、排尿によって体温調節します。
また、自分の排泄物であるフンを食べる食糞とよばれる行動をとります。
吸収できなかった栄養や腸内細菌を再度取り入れる行為です。
人間にとっては異常行動ですが、モルモットにしてみれば必要な行為なので、やめさせないようにしましょう。
モルモットのにおい
モルモットはにおいが強く、ペットとして敬遠されることがあります。
原因は発情期特有の独特なにおいと、お尻の近くにある皮脂腺から出ている分泌液です。
モルモットのオスは一年中発情しており、独特なにおいを発するので、メスよりオスのほうがくさいと言われています。
皮脂腺から出る分泌液には独特のにおいがあり、モルモットの肛門付近にあるため、尿などの排泄物に分泌液が付着することによって、においが強くなってしまいます。
これがにおいの原因になるので、お尻の近くを清潔にしてあげることでにおいの対策をすることができます。
また、床材として敷き詰めた牧草がにおいの原因になることもあるので、ケージの中を掃除して清潔に保ったり、市販の安全な消臭スプレーを使用しにおい対策をしてストレスなくモルモットを飼育しましょう。