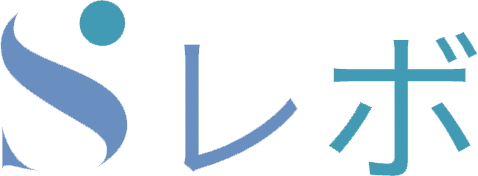ファンシーラットは最近では家庭用ペットとして人気の高い動物です。その理由が「賢く社会性のある動物・多頭飼いが出来る・人間に懐きやすい」といったペット初心者でも飼いやすいというところ。
今回はそのファンシーラットについて詳しく解説していきます。
ファンシーラットとは?

それでは早速ファンシーラットの特徴は歴史などについて紹介していきます。
ファンシーラットの歴史
ファンシーラットは、哺乳網ネズミ科クマネズミ属に分類される、家畜化されたドブネズミです。
ドブネズミというと感染症などのリスクが気になりますが、ファンシーラットは何世代にも渡り品種改良されてきており、リスクは一般のペットと変わりありません。
18世紀頃、ヨーロッパでドブネズミを捕獲するネズミ捕り屋と呼ばれる商いをしていた人たちによって、ブラッドスポーツという見せ物にドブネズミを使用したことがファンシーラットの起源と言われています。
また珍しい色のネズミを取り除き、改良販売していたことでファンシーラットがペットとして定着しました。
体の特徴
体長は約25㎝程で、尻尾の長さを入れると40㎝くらいになります。
体重250g~500gほどでネズミの中では大きい部類に入ります。
性格の特徴
ファンシーラットは長い間、人間に管理されてきたため、とても穏やかで人に慣れやすい性格をしています。
警戒心が強く、臆病な面もありますが、学習能力も非常に高いため、コミュニケーションもとりやすく、懐きやすい動物です。
社交性も高く、基本的には群れで行動する動物なので、多頭飼いに向いています。多頭飼いの場合は、繁殖しすぎないように注意することが必要です。
ファンシーラットの種類
ファンシーラットはペットとして品種改良されてきた歴史があるので、様々な毛色と模様の種類が存在します。
基本的には毛色×模様で個体の品種が決まってきます。ここでは代表的な毛色と模様を紹介します。
【毛色】
・アグーチ色系
| シナモン | アグーチより明るく優しい茶色。 |
|---|---|
| フォーン | トパーズとも呼ばれ、美しいオレンジ色。 |
| アンバー | アージェントとも呼ばれる。フォーンよりも明るく黄色い。淡く美しいクリーム色。 |
・黒色系
| ブラック | 全身ツヤがあり、単色の黒い色。 |
|---|---|
| チョコレート | ブラックに似ているが、少し焦げ茶色がかった色。 |
・ブルー系
| ロシアンブルー | 濃い灰色。 |
|---|---|
| ブルー | グレーとも言われる灰色。標準的なブルー色。 |
・白色系
| ピンクアイドホワイト | 赤目のアルビノ個体色。 |
|---|
※アルビノとは、動物の突然変異個体を言い、体色が白色で目が赤い個体を総称して言われる。他の動物でもアルビノ個体はよく見られることが多い。
【模様】
| バークシャー | 背面が有色で、お腹の色が白色の個体。 |
|---|---|
| キャップ | 頭のみに色がついている個体。 |
| フーディッド | 頭頂部から背骨(尾までの場合も)まで色がついていて、鞍型の模様をしている。 |
ファンシーラットの値段について

ここでは、ランシーラットの値段と販売場所について解説していきます。
ファンシーラットの値段
ファンシーラットの値段は、だいたい1,000円〜3,000円くらいで販売されることが多いです。
カラーマウス500円〜1,000円、パンダマウスやスナネズミ1,000円〜3,000円くらいなので、ファンシーラットが特に高価という訳じゃないですね。
またファンシーラットは、爬虫類などの生餌として売られている場合もあります。
この場合だと500円〜800円と、少し安価に販売されています。
ペット用として売られている場合も、生餌として販売されている場合も特に違いはないようです。
ただペット用として売られている場合のほうが、繁殖〜成長する過程で大切に育てられ、人間にも懐きやすいので、出来ればペット用として売られているファンシーラットをすることをおすすめします。
ファンシーラットの販売場所
比較的安く買えるファンシーラットですが、どこで販売されているのか解説していきます。
大型ペットショップ
ペットとして流通量が少ないファンシーラットですが、様々な生き物を取り扱う大型ペットショップの場合、まれに販売されていることがあります。
珍しい小動物を取り扱っているお店で販売していることが多くあるので、問い合わせてみるとよいでしょう。
またお店にいない場合でも、取り寄せてくれる場合もあるので、お店の人に確認するのがよいでしょう。
専門店
ラット専門店は実店舗だとあまり見かけませんが、「エキゾチックアニマル専門店」でファンシーラットを探せば、見つかる可能性が高いです。
エキゾチックアニマルとは、明確な定義はないですがペットとして一般的でない動物を言うようです。
ただペットとして人気のあるモルモットなどもエキゾチックアニマルに含まれることもあるので、犬、猫以外のペットとして飼育される動物を総称して「エキゾチックアニマル」と呼ぶと考えた方がよさそうです。
ネットショップ
ネット上で検索すれば、ファンシーラットを取り扱っているお店が見つかり、実店舗より安い値段で個体が買えることがあります。
ただネットショップで生体が販売されている場合、トラブルが多いのが現状で、注意も必要です。
ネットの場合、実際の動物の体の弱さや、病気がちの個体か、など分からない場合も多く、輸送時のストレスなども考えると、販売場所は慎重に行うようにしましょう。
その他
上記以外にも、ブリーダーが直接販売していたり、里親募集でファンシーラットが見つかる場合があります。ネット上のホームページや、里親募集サイトを探してみるとよいでしょう。
また下記サイトは幅広い種類のファンシーラットを取り扱っているので、おすすめです↓
ファンシーラットの寿命について

ファンシーラットをペットとして家に迎えた場合、どのくらいの寿命なのか、また他の小動物の寿命との比較しながら解説していきます。
ファンシーラットと小動物の寿命について
犬や猫に比べて、小動物の寿命は短いですが、実際どのくらいの寿命なのでしょうか。
| ファンシーラット | 2年〜3年 |
|---|---|
| パンダマウス | 1年半〜3年 |
| ハムスター | 2年前後 |
| うさぎ | 5年〜6年 |
| フェレット | 7年〜8年 |
他の小動物と比較してみても、ファンシーラットが特別寿命が短いという訳ではなさそうです。
ただだいたい2年〜3年ぐらいで亡くなってしまうことが多いので、飼育するときは寿命のことも考えて飼ったほうがいいです。
ファンシーラットを飼育する場合の注意点
小動物を飼育する場合、ちょっとしたことが体調不良の原因につながりなりかねません。ここでは、ファンシーラットを飼育する上での注意ポイントを見ていき、寿命を少しでも伸ばせるよう気をつけるポイントについて解説していきます。
主に気をつけておきたいポイントが以下の3つになります↓
- ストレス
- 適度な運動
- 病気
ストレスについて
ファンシーラットは、人によく懐き、コミュニケーションをとるのが好きな動物です。
また社会性もあるので1匹で飼育するより、複数匹で飼育したほうがストレスが少なくなるでしょう。
ストレス軽減の方法としては、ケージ内に遊び道具として滑車やかじって遊ぶ道具を入れてあげ、ケージ内でも遊べるような空間作りをしてあげるのが大切です。
適度な運動
飼育に慣れてくると運動不足解消のためにも、ケージから出して部屋の中で遊ばせることもしてあげたほうがよいでしょう。
ただしケージの外で遊ばせる場合は、以下の点に注意が必要です。
- 逃げないように注意する。
- 家具の裏などの隙間に入らないように、目を離さない。
- おしっこやフンに注意。
- 犬や猫などを飼っていたら、同じ部屋で遊ばない。(犬や猫は、小さなファンシーラットに攻撃する恐れがあるため)
病気
ファンシーラットの病気の一つに歯の不正咬合があります。不正咬合とは、前歯が一生伸び続ける「げっ歯類」に属する哺乳類によく見られる症状で、噛み合わせが悪いことを意味しています。
ラットは常に伸び続ける常生歯を持っているため、歯の伸び過ぎに注意する必要があります。
基本は牧草などををよく噛んで食べることで歯が摩耗し、歯が伸びすぎるのを防いでいます。ただ繊維質の少ないエサを食べていると、不正咬合を発症することがあります。
不正咬合になってしまうと、食欲が減退し違う病気にもなりやすく、命にもかかわってきてしまうので、積極的に繊維質の多いものをエサとして与えましょう。
また、ケージ内にかじるものを入れてあげると、かじって遊ぶ時に歯が削れ、不正咬合の予防になります。
この他にも、ファンシーラットは尿路結石症、便秘、腎不全などの病気にかかりやすいといわれています。飼育時には、注意してあげましょう。
ファンシーラットはなつくの?

ファンシーラットはドブネズミを家畜化した動物ですが、長年にわたり品種改良が重ねられ、性格は温和で人懐っこい性格をしています。
とても賢く、人間が言った言葉も少しですが理解する力があります。そのため、ペットとして飼育していく中で、とてもよく懐かせることが出来ます。
ここでは、どのような個体が懐きやすいのか、懐かせるポイントを細かく見ていきます。
懐きやすい個体は?
まず性別でみるとオスのほうが懐きやすいです。
ファンシーラットは、メスよりオスのほうが性格もおっとりしていて、飼い主に甘えてくる個体が多いようです。個体の性格にもよりますが、べったり甘えて懐いてほしい場合は、オスを選ぶとよいでしょう。
ペットショップ、ブリーダーの育て方にも違いが
ファンシーラットを家に迎える前に育てられていた環境によっても、違いが出ます。
ペットショップや、ブリーダーに可愛がられ、人間に慣れている場合と、そうでない場合には懐きやすさが変わってきます。
購入する時にすぐ近寄ってきてくれる子や、手に乗ってきてくれる子など懐きやすい個体を選ぶと、家に迎え入れてから早く懐いてくれるでしょう。
またブリーダーから購入する場合は、母親の性格から子供の性格が分かります。
母親の性格は遺伝しやすいので、人懐っこい性格の母親から生まれた個体を選ぶことで、懐く可能性が高くなるでしょう。
懐かせるポイントは?
飼育当初は、無理にコミュニケーションをとらない方がいいです。
ファンシーラットを含め、小動物は環境の変化に弱く、家に迎え入れてすぐに環境に慣れません。
この時に、必要以上に触ったり、撫でたりすることで、ファンシーラットにはストレスになってしまいます。嫌がっているのに触ったりしていると、恐怖のあまり噛んでくる個体もいます。
懐かせようと思っても逆効果になり、慣れるまでに時間がかかってしまいまうことがあるので、注意しましょう。
飼育は1匹のほうが懐きやすい
ファンシーラットは1匹で飼育するよりかは、複数匹で飼ったほうがよいと言われています。
それは、社会性のあるファンシーラットが、仲間を大切にし、コミュニケーションをとって生活する習性があるためです。
ただ複数匹で飼育することで、仲間同士で助け合い、安心感が出てしまうので、飼い主に懐きにくくなる傾向があると言われます。
1匹で飼育することで飼い主を仲間だと思って、懐いてくれます。ただ1匹で飼育すると、コミュニケーション不足がストレスになりやすいので、注意が必要です。
隠れる場所は少なくする
小動物を飼育する場合、隠れる場所を作ると安心するといったことがありますが、ファンシーラットの場合、隠れる場所を少なくすことで、飼い主に懐きやすくなります。
ファンシーラットは狭く隠れやすい場所が好きなので、隠れ家を作ってしまうと、なかなか出てこなくなります。出てこないと懐かなくなるので、なるべく隠れる場所は少ないほうがよいでしょう。
スキンシップをとる
慣れてきたら、なるべく撫でたりしてスキンシップをとってあげましょう。耳の後ろを撫でると、喜ぶ子が多いです。
また、手からおやつや主食のペレットをあげて慣れさせましょう。最初のうちは、警戒しておやつを食べてくれませんが、慣れてくると食べてくれるようになります。
ファンシーラットの飼育に必要なもの

飼育に必要なものは以下になります。これに、ファンシーラットの個性に合わせた飼育用品を揃えましょう。
- ケージ
- 床材
- 寝床
- 回し車
- 食器(エサ入れ)
- エサ
- 給水器
- その他(かじり木など)
飼育に必要なものを、細かく見ていきます。
ケージ
ケージとは檻やカゴのことです。ケージは、市販品(プラスチックタイプ)、水槽タイプ、金網タイプなどがあります。
ファンシーラットは、意外と大きく大人になると体長は25㎝くらいになりますが、子供の時は小柄なため、金網タイプのケージの場合、脱走する可能性があります。
水槽タイプは高さもあり脱走しづらく、透明なので内部が見やすいですが、通気性が悪く掃除がしづらいなどデメリットもあります。
ケージはタイプ別にメリット、デメリットがあり、飼育環境や飼育状況によっても最適なケージは変わってきます。
飼い主がストレスなく、飼育出来るケージを選ぶことが重要です。
床材
ファンシーラットのフンや尿は、独特な刺激臭がします。このため、掃除しやすいタイプの床材をひくことをおすすめします。
床材は掃除のためだけでなく、ファンシーラットの足にかかる負担も減らせます。
ファンシーラット専用の床材はないので、ウサギ用や、小動物用の床材を利用しましょう。砂タイプや、チップタイプなど色々あるので、飼育しやすいものがよいでしょう。
多くの小動物の床材として使用されているウッドチップは、アレルギーの原因となる個体もいるため、くしゃみなどアレルギー症状が出たら、使用を中止して他の床材に交換するのがよいでしょう。
またペットシートは、掃除がしやすいですが、ファンシーラットがかじって飲み込んでしまうと危険なので、避けた方がよいでしょう。
寝床
ファンシーラットの寝床として、ベッドタイプ、ハンモック、ハウスタイプがあります。個体によって好みは違いますが、人気なのはゆらゆら揺れるハンモックです。ハンモックは、小動物用のものが市販されています。
ファンシーラットは、子供の時は小さいですが、成長すると25㎝くらいになるので、体の大きさに合わせて、安全性、耐久性をチェックし選びましょう。
回し車
回し車も運動不足やストレス解消のために、飼育用品としておすすめです。小動物用の回し車は色々なタイプがあるので、下記条件を確認しましょう。
【ファンシーラットにおすすめの回し車】
- 音が静かなサイレントホイール
- 尻尾や足が挟まれないような作りの物
- すぐ倒れてしまわないような作りの物
- 回し車でおしっこをしてしまうこともあるので、なるべく洗いやすい物
食器(エサ入れ)
ファンシーラット専用の食器はあまり売っていないので、体に合った食器がよいでしょう。
木製やプラスチック製はかじってしまうことがあるので、陶器製のエサ入れがおすすめです。
Amazonや楽天などでも陶器製の餌入れは数多く販売されているので、簡単に購入することはできます。
陶器製の餌入れも色んな種類があるりますが、ファンシーラットには下記のようなシンプルな餌入れがおすすめです。
エサ
エサは市販の小動物用フードや、ハムスター用ペレットなどが栄養バランスもよく、簡単にあげられます。(ペレットとは、人工的に作られた栄養分が濃縮されている固形のエサです。)
またおやつには、野菜や果物を少量与えてあげるとよいでしょう。(牧草も食べることがあります。)
ファンシーラットを含む小動物は、食べ過ぎて体調不良になってしまうことがあります。飼い主がバランスよく、量を調節してエサを与えることで、健康管理をしてあげましょう。
最近はファンシーラット専用も販売されるようになっていますので、ファンシーラットを大事に育てるなら専用フードがおすすめです。
専用フードはAmazonや楽天でも購入可能なので、いつでも買うことができます。
給水器
ファンシーラットは、飲み水を皿タイプの容器に入れてあげても、排泄物で汚れることが多くあります。
皿タイプの飲み水容器よりも、衛生上給水タイプがおすすめですが、ファンシーラットの中にはうまく飲めない個体も存在します。
上手に飲めているか確認し、上手に飲めない個体には皿タイプの容器に水を入れてあげましょう。
その他(かじり木など)
ファンシーラットはげっ歯類と呼ばれ、歯が永遠に伸び続けるため、歯でかじって長さを調節する必要があります。
かじり木を入れてあげることで、歯が伸びすぎるのを防いだり、ストレス解消に役立ちます。
ファンシーラットとハムスターの違いは?

ファンシーラットもハムスターもどちらもネズミ科の動物ということもあり、似ているところがある両者。
とはいえもちろん違う部分はあるので、ここではファンシーラットとハムスターの違いについて説明していきます。
まずハムスターの特徴は生活スタイルが夜行性です。
視力が悪く、匂いや音を頼りに行動します。基本的には臆病な性格の子が多く縄張り意識が強い、他のハムスターと激しくケンカすることもあります。
繊細な性格でストレスに弱いです。掃除のし過ぎや洗濯機などの生活音もストレスになる原因になることもあります。
それによって、気性が激しくなるハムスターもいるほど。ハムスターは群れる生き物ではないため一頭個別飼育が基本となります。
これらがハムスターの基本的な特徴となります。
次にファンシーラットの特徴を説明していきます。
ファンシーラットはドブネズミの仲間です。もともとは18世紀ごろのイギリスでドブネズミがペット化されたことが始まりです。
種類はドブネズミですが、野生の個体と違って清潔なので安心して飼育はできます。
ちなみに野生の個体は寄生虫やダニやノミなどに寄生されている可能性が非常に高いので、見かけても触れないようにしましょう。
人懐こく穏やかな個体が多いのもファンシーラットの特徴です。犬や猫のようにスキンシップを好む個体が多いです。
また、ラットの賢さは犬並みと言われています。きちんとしつければトイレを覚えたり、仕込めば芸を覚えてくれることもあります。
最初は人に怯えてしまう子もいると思いますが、時間がたてば自然に慣れてくれます。ラットの嫌がることをせずにいれば時間はかかりません。
また、毛皮が濡れることをあまり好まないので、余程汚れてしまったとき以外に温浴をさせることはあまりおすすめできません。温浴が好きな個体もいますから、一概には言えませんができるだけ避けた方が良いでしょう。
小さなスペースで飼うことができるので、マンション等での一人暮らしの方にも最高のパートナーとなります。ただし、寿命は2~3年ほどです。残念ながら、長く一緒に暮らすことのできる生き物ではありません。飼育するときは寿命のことを念頭に置いて大事に飼ってあげてください。
ファンシーラットは一度痛いことや恐怖を覚えるようなことがあるとラットは飼い主にも怯えてしまいます。そのため、粗相やマーキングをしても叱らないことです。粗相をした、マーキングをしたといっても犬や猫のように大量に尿をするわけではありません。寛大な心をもって接しましょう。
ファンシーラットは群れで活動するネズミです。そのため、社交性が高く多頭飼いをすることもできますし、何より人になつきやすいという性質を持っています。
ファンシーラットは一匹だと寂しがってしまう場合が多いです。もちろん個体同士の相性が悪ければ喧嘩もしますし、つがいを同じ飼育ケースに入れてしまうと繁殖してしまうという問題もあります。
同腹の兄弟であればお互いが怪我をするような喧嘩をしたりすることはないと言われていますが、多頭飼育を行いたい場合はその点に注意をすることが必要です。
以上の特徴から、ファンシーラットとハムスターの違いをまとめるこうなります。
ファンシーラットとハムスターの違う部分はこれだ!
- 体の大きさと尻尾の長さ
- 群れで生活を好むかどうか
- ストレスに強いかどうか
ファンシーラットは群れを好みストレスにも強いので、飼いやすい動物ですよ。
ハムスターやモルモットの似たフォルムでその小ささが魅了のパンダマウス。ただ通常のペットショップでは販売されていたりいなかったりと購入場所が意外に悩むことも。そんなパンダマウスの購入場所や何を食べるのか?値段や飼育に必要なものなど実際に飼う時[…]