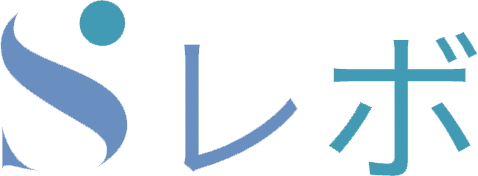一輪一輪が可愛く咲き、花の色も多数あり家庭用で育てるお花として人気が高い「サイネリア」。今回はそんなサイネリアについてご紹介していきます。
育て方について

冬に見かけることの多い花ですが、寒さにはあまり強くないため、12月以降は室内の日当たりが良い、窓辺などの場所で育てるようにしましょう。
特に市販で売られている苗などは温室で生産されたものが多く、寒さには慣れていないため、注意が必要です。真冬でも5℃を下回らない暖かい地域であれば、徐々に寒さに慣れさせていくことで、屋外での冬越しも可能となります。乾燥や高い湿度にも弱いため、室内で育てる場合は暖房などの風が強く当たらないようにしましょう。
水やり
土の表面が乾いていたら、水を与えるようにしましょう。
サイネリアは本来多年草の植物ですが、日本の夏のような温度と湿度の高い環境には耐えることができないため、夏前には枯れてしまうことが多く、1年草として扱われています。
挿し芽などを行わずに夏越しはすることは難しいでしょう。
冬になってサイネリアが開花を始めると、土の中の水を吸い上げる力が強くなります。水切れを起こしやすい種類でもあるため、しっかりと水を与えるようにしましょう。
葉や花びらに水が当たってしまうと湿度が高くなってしまったり、花が痛む原因になるので、水は土に注ぐようにやさしく与えるようにしてください。
また庭植えなど屋外の場合は雨が当たらないように、軒下などに植えるようにしましょう。
肥料・追肥
元肥にはリン酸が多く含まれた緩効性の肥料を施すといいでしょう。地上部のボリュームがあるサイネリアは、開花が始まる頃には元肥だけでは養分が足りなくなることが多いです。
花つきの良い状態を維持するためにも、生育期や開花時期である9月〜4月のあいだは10日に1回程度の頻度で、薄めの液体肥料を用いて追肥を施すようにするといいでしょう。
用土
水もちが良く、有機質が多く含まれた土を使用するといいでしょう。赤玉土5、ピートモス3、バーミキュライト2程度で混ぜ合わせたものに緩効性肥料を適量混ぜ込みましょう。
市販の草花用培養土では養分が足りなくなったり、水もちが十分でないこともあるため、堆肥やピートモスを適量混ぜ合わせておくといいでしょう。
植替え・植付け・種まき
サイネリアの種まきや苗植えは、9月頃に行うのが適しています。冬の時期などにすでに開花した状態の株を手に入れた場合は、そのまま植え付けて育てましょう。
種を発芽させるためには、15℃〜25℃ほどの温度が必要になります。
発芽には日光が必要になるため、種の上から土は被せず、土の中が乾かないように水をしっかりと与え、葉が6枚以上になってから鉢やプランターに植え付けるといいでしょう。
肥料は必要ないため、赤玉土を用いた育苗ポッドなどで発芽させることができます。種から育てたサイネリアは市販の苗に比べて、開花時期がやや遅くなりますが、寒さに強い株を育てることができます。
鉢植えの場合、苗の植え付けは一回り大きいサイズを用意しましょう。市販の鉢植えを購入した場合、根詰まりを起こしていることもあるため、大きな鉢に移してあげた方がいいでしょう。
日本では夏前に枯れることが多く、1年草として扱われているため、それ以外での植え替えは基本的には必要ありません。
注意すべき病気・害虫
サイネリアで気をつけるべき病気としては、灰色カビ病やうどんこ病があります。
灰色カビ病は細菌によって発症する病気です。9月〜12月頃の温度が低く、湿度が高い環境で発生しやすく、サイネリアのような冬に花を咲かせる植物では感染することが多くあります。
症状としては、溶けるように葉や茎が腐らせたり、花に白い斑点をつくり、やがて灰色のカビが全体に広がっていきます。一度発症すると治療することはできないため、発症部分は切り取って感染を防ぎましょう。
うどんこ病は9月〜10月頃、湿度の高い環境で多く発生します。カビが原因となる病気で、葉の表面や株全体を粉のように白っぽく染めていき、光合成や生育を阻害します。
症状を確認した場合は薬剤などを使用して、カビが繁殖しないようにしましょう。
灰色カビ病もうどんこ病も高い湿度を好むため、風通しの良い環境を維持するなどして予防することが大事です。
害虫ではアブラムシやコナジラミに注意が必要です。アブラムシや葉や茎、コナジラミは葉の裏など風通しの悪い環境が続くと発生しやすくなります。
栄養が吸われることで生育が悪くなるだけではなく、アブラムシやコナジラミの排泄物からすす病などが引き起こされる危険もあります。
見つけ次第、テープで引き剥がしたり、数が多い場合は薬剤を用いて駆除するようにしましょう。
管理温度
スペインのカナリア諸島が原産地であるサイネリアは安定した気温を好むため、厳しい寒さや暑さには弱い種類の植物です。生育の適温は10℃〜20℃ほどとなっており、発芽には15℃〜25℃が必要となります。
日本では夏の暑さに耐えることができないため、1年草として扱われることが多いです。冬も0℃を下回る環境では枯れてしまうため、室内に取り込むようにしましょう。
増やし方について

サイネリアは、挿し芽で増やすことができます。挿し芽は4月下旬〜5月が適した時期になります。
暑さに弱いため苗のままでは夏越しが難しいサイネリアですが、挿し芽を行うことで育て続けることができます。
花茎を一度切り落とし、株元から出てきた新しい芽を摘み取って挿し芽に使います。
土はよく湿らせた赤玉土を用意し、定期的に水やりや肥料を施しましょう。
成長して大きくなるごとに、サイズに合った鉢へ移し替えます。
夏の時期は高い温度と湿度を避けるため、風通しの良い明るい日陰や半日陰で管理をするといいでしょう。
>品種について

サイネリアには主に5つの品種があります。それぞれの特徴にてついてご紹介していきます。
「アーリー・パーフェクション」シリーズ
花径2.5~3㎝の小輪品種。
レッド・ピンク・ブルーなど5色ありまず。コンパクトに育てるならこれ。
「ジェスター」シリーズ
花径3~4㎝の中輪品種。
清の周りが白くなる蛇の目や淡い黄色など7色あるシリーズ。
ムーンライト
シネラリアで初めてつくられた淡い黄色の小輪品種。光線が強いと白くなるので、開花期は薄いカーテン越しの場所に置くと黄色みが強く育てることができます。
「桂華(けいか)」シリーズ
草丈が高い木立ち性シネラリアのシリーズ。
丈夫で野草的な風情が魅力です。
セネッティ
こちらも草丈が高いシネラリアのシリーズです。室内用の鉢物として改良されたコンパクトなシネラリアに、草丈が高く強健な野生種を交配させた非常に丈夫な品種。
サイネリアとは?

一つの株にたくさんの小さな花を咲かせるサイネリア。
花の色や咲き方が非常に豊富で、日本では冬の鉢植えの花として親しまれています。
冬の花壇に色を添えてくれる貴重な品種。暖色で目に鮮やかな景色を楽しむのもよし。
青紫色の花は庭に植えるとキュッとした締め色になり、スタイリッシュな景観を作り出してくれますよ。
日本での生い立ち
葉っぱがフキの葉に似た形であることや、サクラのように株を覆いつくすように花を咲かせることから、1896年に松村博士が「蕗桜(フキザクラ)」と名付けました。
これは、昔の学者の間にあった海外から輸入されたものには必ず和名を付けるという当時の習わしによるものです。
花屋さんでは、富貴菊(フウキギク)・富貴桜(フウキザクラ)などとよばれることもありましたが、一転して英名に合わせて「シネラリア」として流通します。
しかし、最近では「死ねラリア」と連想してしまう人も多く、流通名は「サイネリア」とされ、店頭に並ぶ多くが「サイネリア」と冠しています。
サイネリアの分類
サイネリアは、園芸的に「シネラリア」と呼ばれますが、シネラリア属ではなく、キク科ペリカルリス属の園芸品種群です。
原産地は北アフリカ・カナリー諸島・マデイラ諸島で、14種が自生しており、園芸で親しまれているものは18世紀にイギリスで生まれました。
イギリスで生まれた交雑種から、さらに複数の種を掛け合わせているため、園芸品種成立の交配式はわかっていません。
草丈20~30cmで半球状に育ち、カラフルな花を密にこんもりと咲かせます。
スペイン領カナリア諸島原産のペリカリス・クルエンツス(Pericallis cruentus)、 ペリカリス・エリティエリ(P.heritieri)、ペリカリス・ポピュリフォリウス(P.populifolius)、ペリカリス・トゥシラギニス(P.tussilaginis)を交配して、背が低く半球状に育つように改良された結果、今の姿になりました。しかし、近年では再度野生種と交配され、草丈50~60cm程度に育つ園芸品種もあり、木立ち性シネラリアと呼ばれています。
花言葉について

サイネリアの花言葉には、「快活」や「愉快」、「喜び」があります。
いずれも前向きな言葉なので、大切な人への贈り物や庭植えにそばに置くなど、たくさん触れていたいお花ですね。